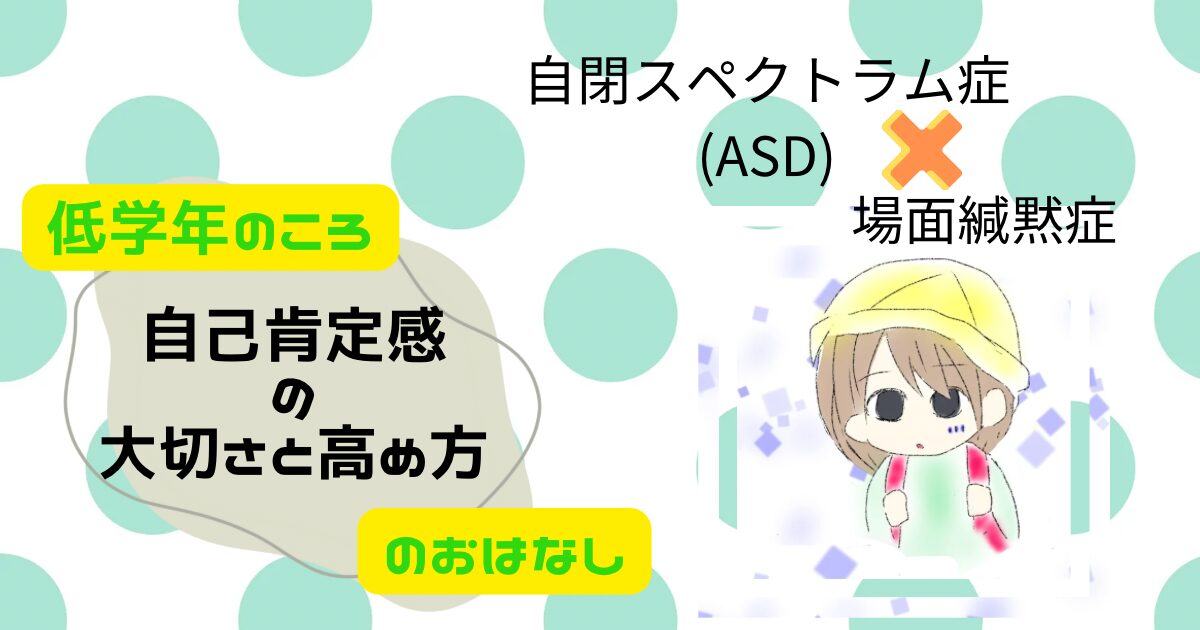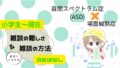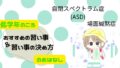いつもみんなの後を追いかけていた小学校低学年のころのふたハです。
場面緘黙症だった私は些細なことで不安を感じてしまうことが多かったです。
そのため、新しいことに挑戦することがなかなかできず、できることが人より少なかったです。
さらに、自閉スペクトラム症(ASD)の特性のせいか、あまり周りを気にしないタイプでした。
”みんなより遅れているから急がないと!”
”みんなよりできないから悔しい!”
…のような気持ちは全くなかったです。
その結果、傍から見たらマイペースな子だったと思います。
私の母はせっかちなタイプで、引っ込み思案な私のことをとても心配していました。
みんなよりもやることが遅い私の姿をみて、いつももどかしそうな様子でした。
このくらいの歳になると、子どもながらに母の様子は敏感に感じていました。
母に言われたことはできるだけやってみようとしましたが、自分の思うようにはできませんでした。
《小学生ふたハ》できることを増やす。家での努力と練習に付き合ってくれた母。
心配症な母は私が自転車やブランコに乗れるように練習によくつきあってくれました。
ですが、保育園の頃と同様に厳しい母でしたので、スパルタ気味でした。

母には何度も怒られ、練習するのが嫌になったこともありました。
でも、できるようになるまであきらめずに取り組み、自転車もブランコも乗れるようになりました。
練習は大変でしたが、できるようになったことで自信と忍耐力がつきました。
私と一緒に辛い練習に付き合ってくれ、できた時に一緒に喜んでくれた母にはとても感謝しています。
《小学生ふたハ》数年かけてマスターした大縄跳び。自信と忍耐力で乗り越えられた!
ふたハが小学校の時にできなくて苦労したのが「大縄跳び」です。
他にもできないことはたくさんありましたが…。
大縄跳びはクラスみんなで一致団結して行うため、できまいままでは避けられないものでした。
小学1年生のうちは飛べない子たちも何人かいました。
しかし、年数が上がる度に、飛べない子は減っていきました。
小学3年生になると、休み時間を使って担任の先生に個人レッスンをしてもらった思い出があります。
その後、飛べるようになりましたが、高学年になるとだんだん目標も上がっていきます。
ふたハの小学校は大縄跳びに力を入れていました。
毎年、跳ぶ回数の目標を決めて1年を通して取り組んでいました。
そして、1回でも引っかかると始めから数えなおすルールでした。
回数が大きくなるほど引っかかった時のプレッシャーはなかなかのものでした。

絶対引っかかりたくない一心で、気合で跳んでいました!
苦労した思い出が多い大縄跳びですが、挑戦したことで得られたものもたくさんありました。
目標を成功できた時に、チームの一体感や達成感の喜びを経験できたのはそのうちの一つです。
ですが、一歩間違えると、登校しぶりの要因になってしまう可能性もありました。
乗り越えられたのは、跳べるようになった自信と最後まで頑張れる忍耐力があったからだと感じます。
《みみコ/繊細/自己肯定感低め》自転車に乗れるまでの道のり。
長女のみみコは元々不安が強く、自己肯定感が低めです。やればできるタイプだと思いますが、エンジンがかかるまでに時間を要します。
みみコの通う小学校では、4年生になると自転車講習があります。自分の自転車を学校に持って行き自転車に乗る授業がありました。
みみコの年長の誕生日に自転車を買いましたが、なかなか乗る機会がなく過ぎていました。
みみコが小学1年生になったころ、そろそろ自転車の練習をしないと…と思い、練習をスタートさせました。
自分が母に厳しく言われて嫌だったので、優しいスタンスで自転車の練習に付き合おうと思っていました。

ですが、なかなか進まないことにイライラしてしまい、母のように厳しく言ってしましました。
その結果、完全にみみコのやる気が消失してしまい、一旦あきらめることにしました。
《みみコ/繊細/自己肯定感低め》子どものやる気が出た時が自転車に乗れるタイミング。
みみコが小学2年生になり、練習するのにちょうど良い気温になってきたタイミングで自転車の練習を再開することにしました。
昨年の反省をもとにみみコと相談して、練習をする上でみみコから要望がありました。
- 練習中は何も言わないでほしい
- 自分のペースでやらせてほしい
自転車の練習ができる公園に行き、坂道を利用しながら何度も何度も練習を重ねて乗れるようになりました。
練習中に気になることはいくつかありましたが、口を挟まず自分のペースでやらせました。
一度乗れたら自信満々な様子で、公園を何周も走り回り、しばらく延々と乗っていました。
負けず嫌いなみみコにとっては、できなくてくやしいのは一番みみコ自身だったと思います。
自分の力で壁を乗り越えられて、とても嬉しそうな様子でした。
自転車に乗れるようになった時期は平均よりも遅いと思いますが、本人のやる気が出た時が乗れるタイミングだと感じました。
《みみコ/繊細/自己肯定感低め》登校をしぶる程嫌だった大縄跳び。大縄跳び克服までの道のり。苦手が自信に変わる瞬間。
みみコの通う小学校でも大縄跳びには力を入れており、毎年全校生徒全員で取り組んでいます。
1、2年生のころのみみコは大縄跳びが上手に跳べませんでした。
大縄大会の時期になると、「学校に行きたくない!」と言って、登校を渋る時期もありました。
私も、大縄大会の時期がくるとみみコのことが心配でした。
担任の先生に相談したり、みみコにプレッシャーがかからないような声かけをするように心がけていました。
みみコが3年生の頃から、少しずつコツをつかんできて、跳べる回数が増えました。
みみコが4年生になって、上手に跳べるようになりました。
跳べるようになって、自信がついたおかげで、大縄跳びが好きになったようです。
大縄大会の時期は毎日練習があります。
「今日大縄ある!やったー!」「大縄楽しみ!」とよく言って登校していきます。
こんなに、人って変わるものなのか…。驚いています。
できることが増えると自信になって、前向きな気持ちになれる!ことを再確認できた出来事でした。