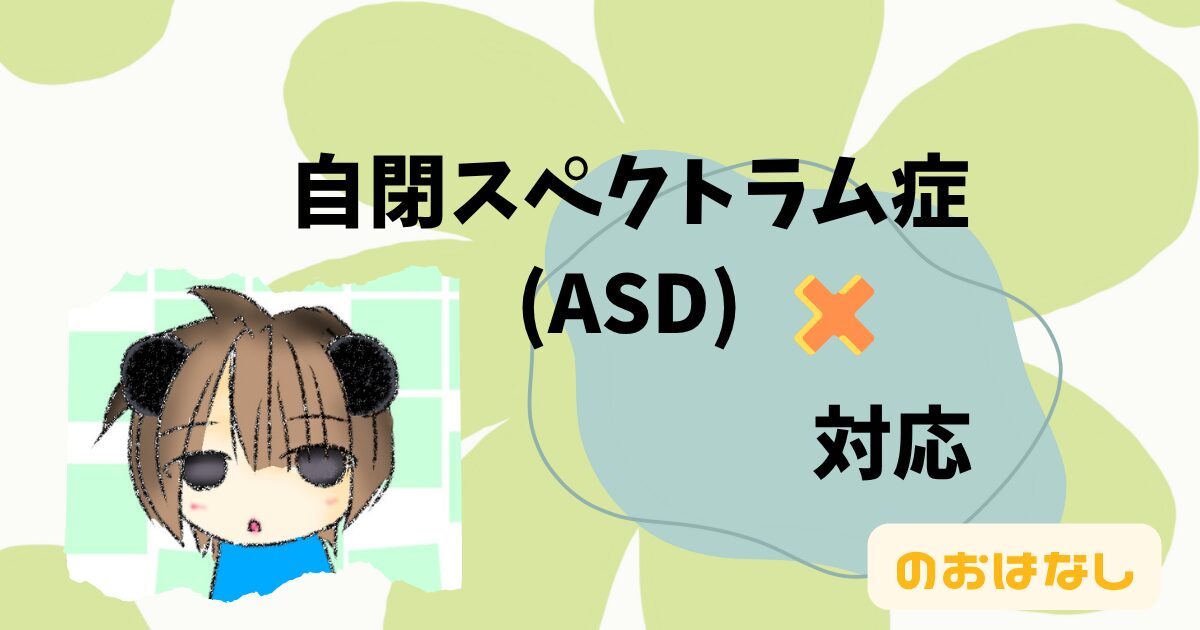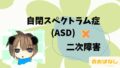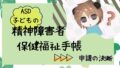ふたハが取り組んでいること
二次障害を防ぐために、以下のことに取り組んでいます。
- 病院(小児科、発達外来、児童精神科)の受診
- 言語訓練、作業療法を受ける
- 療育に取り組む
- 生活習慣を整える
- 放課後デイに通う
- 小学校の担任の先生と密に連絡を取り合う

ぱんタが言葉でのやりとりが難しかったころは、伝えたいことをイラストに描いて教えていました。ぱんタは視覚優位と言われており、耳から入る情報より目から入る情報の方が伝わりやすかったです。そのため、一日の流れをイラストで描いたり、声の大きさや気持ちなどの目に見えないものでも、できるだけイラストで表現して伝えていました。
また、ぱんタは初めてのことや見通しが立たないことは苦手だったので、時計やカレンダーは重宝しています。一時期はアナログ時計とデジタル時計とストップウォッチが三位一体になっている時計が大のお気に入りで壊れるまで愛用していました。予定表は月間と週間のものを用意して、あらかじめイラストで予定を記入して見えるところに貼っています。
生活は起床、昼食、おやつ、夕食、風呂、就寝の時間はほぼ毎日同じ時間で過ごしています。最近は出かけたりいつもと違う予定がある場合は事前に伝えておくと調整は可能で、融通が聞くようになりました。ごはんを食べる場所、勉強をする場所、遊ぶ場所、寝る場所はしっかり分けてあります。
小学校の先生や放課後デイの先生や病院の先生など、困ったことがあれば相談しています。小学校や放課後デイや家庭で困ったことがあればお互いに情報共有をするようにして、対策を話し合っています。
ぱんタが就学前は対応が分からず大変な時期もありました。ですが、小学校入学後は今のところ、小さい悩み事は尽きないものの、大きなトラブルはなく元気に毎日過ごせています。
療育とTEACCH(ティーチ)
発達の遅れが気になって、相談を重ねた結果、最終的に「療育」と出会いました。
療育(発達支援)とは、身体障害や精神障害、発達障害や知的障害がある子ども、またはその疑いがある子どもが自分らしく、自立した生活が送れるよう支援することです。
療育方法にはいろいろな方法がありますが、ぱんタが通っていた療育施設ではTEACCH(ティーチ)という方法を取り入れていました。TEACCH(ティーチ)は自閉症スペクトラム症の特性をカバーするために有効なアプローチ方法です。先ほど、家での取り組みを伝えましたが、療育施設で学んだことが全てベースになっています。
TEACCH(ティーチ)の手法の一部を紹介します。
■物理的構造化
活動別に場所を決めます。「ここは休む場所だよ」「この場所で勉強するよ」など、活動と場所を結びつけます。環境が整理されると、精神的にも安定し、活動や学習へ参加することができるようになります。
イラスト、写真、文字で示し、視覚的に伝えると効果的です。
■視覚的構造化
実物、イラスト、写真などを通してコミュニケーションを整理する方法です。指示や意思表示をする時に、絵カードを有効活用し、「伝わった!」とコミュニケーションの第一歩を踏み出すことができます。
自分の気持ちを伝えたくてもうまく伝えられない、発語によるコミュニケーションに困難を抱えている子どもにとって有効なアプローチです。
参考:TEACCHとは?ASD(自閉スペクトラム症)の人々を生涯支援するプログラムの概要を紹介【専門家監修】【LITALICO発達ナビ】