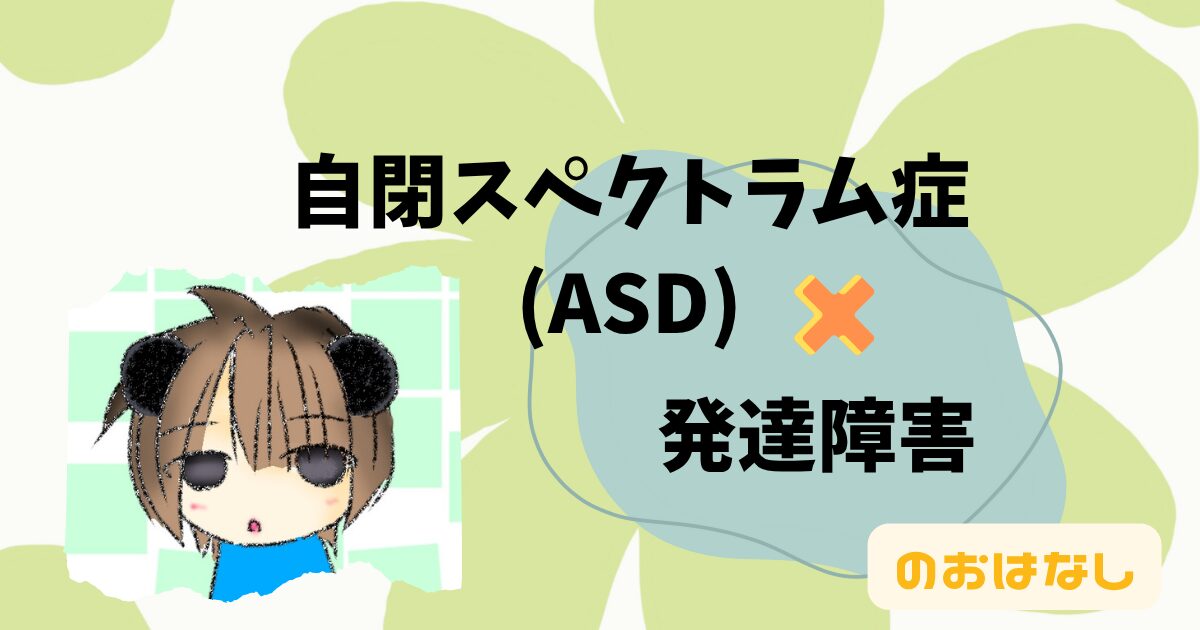発達障害の定義
日本の文部科学省の発達障害の定義は以下のようになっています。
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
日本では発達障害は「障害である」とされています。今まで周りの子どもたちと同じように子育てをしてきたのに…自閉スペクトラム症の診断が出た瞬間に障害児となる現実。診断直後は目の前の世界が一変したような感覚でした。受け入れて前に進むのにかなりの時間がかかりました。療育をしたら治るのでは…病院で言語訓練や作業療法を受ければみんなに追いつけるのでは…と思い、療育で頭がいっぱいだった時期もありました。「障害」という言葉にとらわれすぎて、ぱんタの存在を見失いかけていました。
発達障害は治りません。でも、今の私は「障害=特性」だと考え、ぱんタの特性を上手く活かすためにはどうしたらよいのかを日々考えています。みんなに合わせてぱんタの特性を変えるのではなく、ぱんタの特性を受け入れて、将来ぱんタが自立できるようにサポートしていこうと前向きに考えらるようになりました。

発達障害の受け止め方は人によって違うよ。
「脳の特性」や「個性の延長線」であるという考え方もあるよ!
発達障害の種類

発達障害には大きく3つの種類があります。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 学習障害(LD)
☆自閉スペクトラム症(ASD)
人とのコミュニケーションにおいて苦手や困難さがある、こだわりの強さ、感覚の偏りを特徴とする発達の障害
☆注意欠如・多動症(ADHD)
不注意(集中できない、物忘れが多い)、多動性・衝動性(じっとしていられない、順番を待てない、過度なおしゃべり)を特徴とする行動の障害
☆学習障害(LD)
学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。
それぞれの症状の程度は様々で、症状が共存していたり、ASDやADHDは知的な遅れを伴うこともあります。気になる場合は小児科や児童精神科の専門の先生に診てもらうことをおすすめします。

ぱんタが2歳の時は、おちつきがないことが一番気になっていたので、ADHDを疑っていました。

ASDとADHDは対応の仕方が違うので、診断してよかったです!