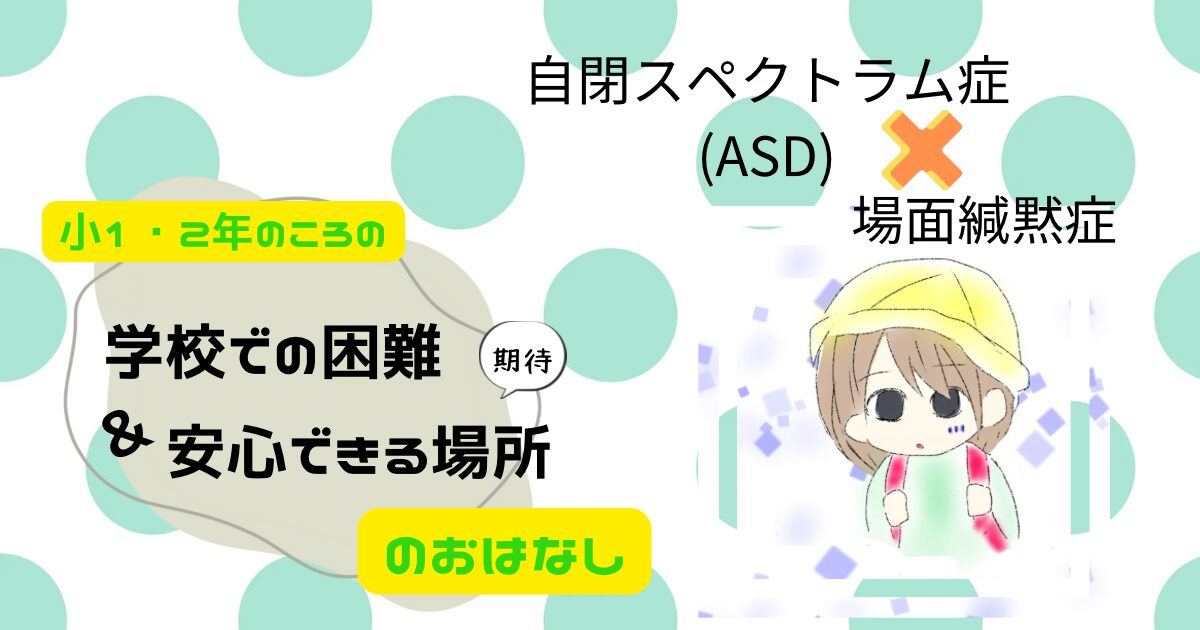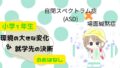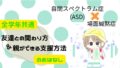《小学生ふたハ》上手く話せないことで苦労したこと。授業中での心理的不安。
小学校になって、自分で話さないといけない場面が増えました。
特に苦手だったのは、授業中に音読や発言をする時でした。
みんなで一緒に読む音読は気持ちに余裕がありましたが、一人ずつ順番に読んでいく音読は嫌でした。どこのパートが回ってくるのかを予測したり、読めない漢字がないか確認をしたり、黙読でリハーサルをしたり。自分の番が回ってくるまでに毎回準備するのが大変でした。
(ふたハの心) 間違えたらどうしよう。読む時に声が震えたら笑われてしまうかも…嫌だな。
いつもドキドキしながら順番を待っていました。
また、先生と視線が合わないように目をそらしたり、あてられたくなくて気配を消すのに必死でした。
しかし、最低限1人1回は発言できるように、手をあげていなくても発言の順番が回ってくることがありました。授業中は一瞬たりとも気が抜けない時間でした。

《小学生ふたハ》大声で泣いてしまった日。言葉で伝えられないコミュニケーションの難しさ。
学校で消しゴムが見つからなくて泣いてしまったことがあります。
友達に伝えて貸してもらったり、先生に「なくした。」と一言伝えれば簡単に済む話です。ですが、困っていることを周りの人に伝えるのは、私にとってはとても難しいことだったのです。

当時の私は、困っていることを先生や友達に言葉で伝えることができませんでした。いつも泣くことで気づいてもらっていました。
他には、嫌なことを言われたときによく泣いていました。言葉で言い返せないため、伝えられる手段が泣くことしかできませんでした。
また、けがをした時も「痛い!」「助けて!」が言えずに、よく泣いていました。
そのため、クラスのみんなにとって、私の印象は、”大人しくてよく泣く子”でした。
《小学生みみコ》授業参観で感じたこと。場面緘黙症があっても安心して授業を受けられる仕組みづくり。
みみコの通う小学校では、1年に3回授業参観があります。
国語の授業を参観した時の話です。
音読は1列ごとに読んだり、読みたい行の時に立って読んだり、複数人で読んでいました。
発言は手を挙げた人にあてていました。発言をした子が次に発言をする子を指名する場面もありました。
(先生)「今の○○さんの答えが合っていると思った人はピースサインで手を挙げてください!」
発言をしなくてもみんなが参加できるような仕組みになっているなと感じました。

当時、私だけと思っていたけど。
音読や発言が苦手な子は多いのかも…。