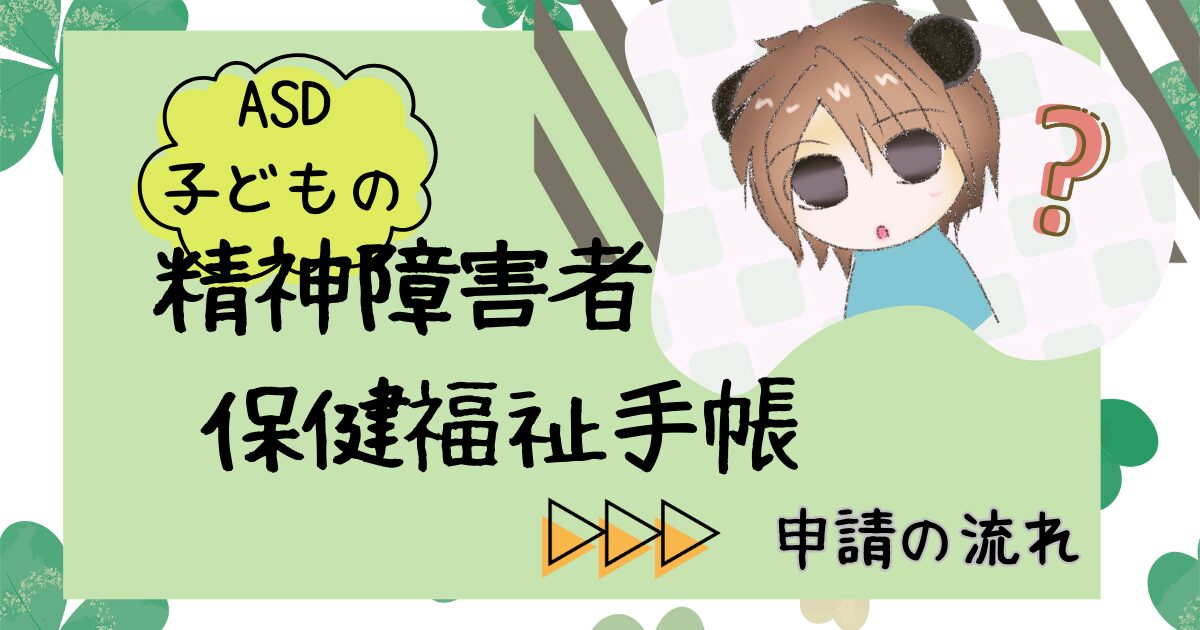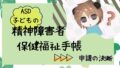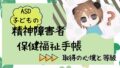我が家はぱんタが小学1年生の時に精神障害者保健福祉手帳を取得しました。
今回はぱんタの精神障害者保健福祉手帳の申請の経緯を振り返りながら、申請に必要なものや申請途中で私ふたハが感じたことについてまとめていきます。
申請方法は各自治体によって異なりますので、一つの例として参考にしてください。
精神障害者保健福祉手帳の申請の流れをイメージしてもらえるよう、実際に私が取り組んだ順にお話していきます!
病院の先生に精神障害者保健福祉手帳が取得できるか相談。
精神障害者保健福祉手帳の申請を決意後。
翌月に定期的に通っているぱんタの発達外来の受診が控えていたので、その時に病院の先生に相談することにしました。
そして、病院の受診日を迎え、主治医の先生に精神障害者保健福祉手帳について相談してみました。
診断書を書いてもらうには、発達障害に係る初診日から6か月を経過している必要があるようです。
ぱんタは既に診断がついていたので、手帳は申請できると確信していました。
ですが、念のため、精神障害者保健福祉手帳を申請できるのか?診断書は書いてもらえるのか?
先生に聞いてみました。
すると、先生は…「できるよ!」と、あっさり一言。

(主治医)「市役所で診断書の用紙をもらってきてください。受付に提出してくれたら診断書の記入をするので準備ができたらいつでも病院にきてください。」
と説明があり、診断書記入の了承を得られてこの日の定期受診は終わりました。
市役所の福祉課に精神障害者保健福祉手帳について問い合わせる。
療育施設を利用し始めた頃からお世話になっている市役所の福祉課。
療育手帳の交付・返納や放課後デイ利用のために何度も訪れているので、私にとっては慣れた場所です。
子どもの場合、保護者が代理で精神障害者保健福祉手帳の申請をできるので、ぱんタ不在のふたハ1人で市役所の福祉課に行きました。
市役所の福祉課の受付で精神障害者保健福祉手帳を申請したいことを伝え、申請に必要な書類の説明を受けました。
診断書の用紙ももらえました。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの(※ふたハの自治体の場合)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- 診断書
- 個人番号(マイナンバー)の番号確認及び身元確認ができる書類

ぱんタの写真はスマホの写真で用意しました。
正面でなかなかいい写真がなくて選ぶのに苦戦しました。

ふたハは市役所に行って用紙をもらいましたが、申請書や診断書の用紙はホームページで入手可能な自治体もあるようです。
事前に自治体のHPを確認したり、電話で問い合わせをしておくと、スムーズに申請できますね!
病院の先生に診断書の記入を依頼する。
市役所でもらった診断書の用紙を持参し、診断書記入の依頼をするために病院の受付に向かったふたハ。
主治医の先生とは前回の受診の際に精神障害者保健福祉手帳についての話が済んでいると伝え、スムーズに受け付けてくれました。
その際、いつまでに診断書を記入してもらえそうか確認しました。
そうしたら、1ヵ月くらいかかると言われました。
特に焦っていなかったので了承し、先生が診断書の記入をしてくれるまで、しばらく待つことになりました。
~1か月後~
病院から診断書ができあがったと連絡がきたので、病院に受け取りに行きました。
病院の用紙で書かれた診断書で用意されており、市役所でもらった診断書の用紙は白紙で戻ってきました。

あれ?
市役所に用紙を取りに行ってと言われたのに…。
ふたハの自治体は用紙の指定はなかったので、全然問題ないのですが…。
少しモヤモヤした気持ちになりました。心が狭いふたハです…。
とはいえ、お忙しい中、診断書を書いてくださった主治医の先生には感謝の気持ちでいっぱいです。
診断書にどんなことが書いてあるのか気になりましたが、中身は開封厳禁でした。
改ざんされないように、しっかり封が閉じてありました。
ちなみに、診断書作成の費用はおよそ2000円かかりました。
市役所の福祉課に提出書類一式を提出して申請完了。
翌日、申請書類一式を提出しに市役所の福祉課に行きました。
提出のみでしたので、手続きは数分で終了しました。
申請の決断をしてから実際に提出するまで2か月くらいかかりました。
そして、交付までに3ヵ月かかるとのこと…。
申請の準備から交付されるまでに、とても時間がかかるので、お気をつけくださいね。

時間がかかったのは、私の段取りが良くなかったのもありますが…💦
以上、申請までの流れでした。
自治体によって異なる部分がありますが、おおまかな流れをイメージしてもらえたら幸いです。
次回は、交付~取得時の体験談をまとめていきます!