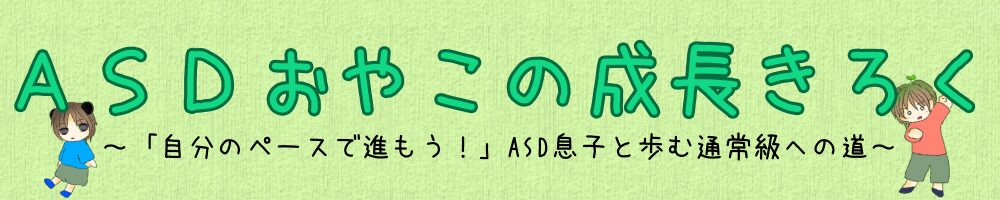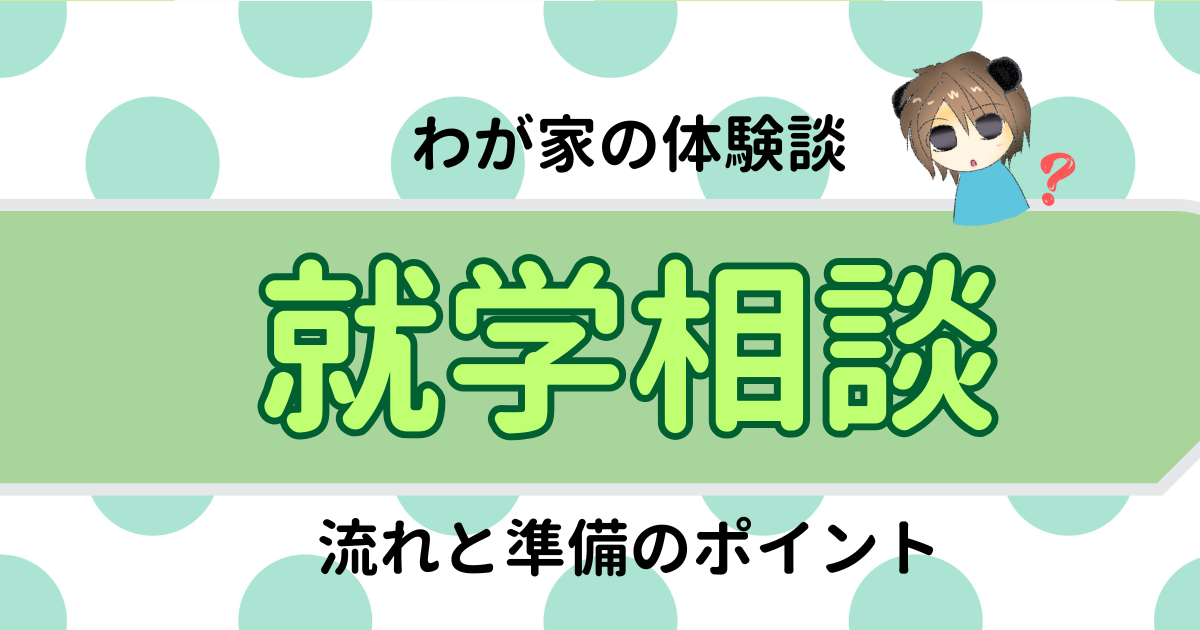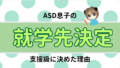こんにちは!ふたハです。
わが家のASDの息子は、幼稚園年長のころに「就学相談」を経験しました。
就学相談は、子どもの特性や発達の様子をふまえて、「通常級がいいのか」「支援級が合っているのか」…などを考える大切な機会です。
でも、正直に言うと、最初は「就学相談って何をするの?」「どんな準備が必要?」と分からないことだらけでした。

身の回りで就学相談をする人が少なく、情報が得られず不安でした。
さらに、就学相談が終わってから「もっとこうしておけばよかった」と思うこともありました。
この記事では、わが家が体験した就学相談の流れや準備のポイントをまとめています。
就学相談を検討しているママやパパにとって、就学相談のイメージが具体的に持て、少しでも安心につながるように情報共有していきます!
就学相談とは?体験して分かった目的と対象
ASDの息子の小学校進学にあたり、市の教育委員会を通じて就学相談をスタートさせました。
最初は「どんなことをするの?」「うちの子も対象なの?」と分からないことだらけで不安でした。
ここでは、わが家の体験を交えながら基本的な就学相談の情報をお伝えしていきます。
就学相談の目的とは?
就学相談は、小学校入学を前に、お子さんに「どんな学びの場が合っているのか」を考えるための機会です。
よって、就学相談の一番の目的は、子どもに合った学びの場を保護者が教育委員会や専門家と一緒に考えることです。
具体的には、「通常級か支援級か」「特別支援学校の方が合うのか」「学校生活をスムーズに送るためにはどんな支援が必要か」などについて話し合います。
わが家の場合は、療育園の先生から事前に就学相談の情報を聞いたり、療育の先輩ママから就学相談を受けた話を聞いていたので、息子が年中くらいの時には就学相談を受けようと決めていました。
実際に、就学相談の場では息子の得意・不得意や配慮が必要な場面を丁寧に聞き取ってもらえました。
就学先の判定だけにとらわれるのではなく、子どものための学びの環境を一緒に考える場である意識を持つと気持ちが楽になります。
どんなお子さんが対象なの?
就学相談は、発達や行動、学習面に不安があるお子さんが対象です。
具体的には、ASDやADHDなどの診断を受けている子だけでなく、「集団行動が苦手」「言葉の発達がゆっくり」「体の使い方が不器用で学校生活が心配」といった子も対象になります。
診断の有無に関わらず、少しでも学校生活に不安があるなら相談してOKです。
就学相談を申し込むタイミングはいつ?
就学相談の申し込みは、小学校入学の前年(保育園・幼稚園の年長)の春〜夏頃が一般的です。
自治体によっては時期が決まっているので、教育委員会や市のHPで確認してみましょう。

私の住んでいる自治体では、5月からの受付・実施でした。
わが家の場合は、幼稚園から就学相談の案内が全員に配布され、年長の5月に申し込みました。
少し早めに動いたことで、6月に面談を受けられ、その後の準備にも余裕を持てました。
就学相談の全体の流れ~わが家の一例~
次に、「就学相談がどんな流れで進むのか」をみていきましょう。
全体の流れを事前に知っておくと、準備をスムーズに進めやすくなります。

息子の一例をもとに就学相談の進み方を解説します!
地域や自治体によって多少の違いがありますので、おおまかなイメージの参考にしてください。
①就学相談に申し込む(保護者)
まず、市区町村の教育委員会に就学相談を申し込みます。
電話や書類での申し込みが一般的ですが、自治体によって異なるので、お住まいの自治体のホームページを確認してみましょう。
自治体のフォームページから申込書をダウンロードして郵送したり、電子申請で申し込みができるところもあるようです。

いろいろな手段があるので、やりやすい方法で申し込みましょう!
ちなみに、わが家は幼稚園から就学相談の案内文書を受け取ったので、必要事項を記入して、幼稚園を通じて文書で申し込みました。
②教育委員会の担当者との面談(保護者と本人)
面談日の案内文書を受け取る
申し込み後、幼稚園を通じて面談日の案内文書を受け取りました。
なお、文書には面談の日時や場所が記載されており、文書と一緒に子どもの情報を記入するための「就学相談シート」用紙が同封されていました。
- Q「就学相談シート」にはどんな内容を記入するの?
- A
私の自治体では次のような内容を聞かれました
- 住所・連絡先・家族構成
- 現段階での就学先の希望
- 子どもの健康や生育歴
- 園での支援や配慮している内容について
- 病気・障害に関わる医療機関や検査の結果(あれば記入)
- 子どもの日常生活の様子
- 子どもの気になるところ
そして、「就学相談シート」は面談当日までに記入して、持参しました。

ちなみに、面談の日程の都合が合わない場合は、変更してもらえます。
早めに連絡して、日程を再度調整しましょう!
教育委員会の担当者との面談当日の様子
教育委員会の担当者との面談当日は、息子と一緒に行きました。
お子さんの同席は可能な限りでよいと案内文書に記載されていましたが、直接息子の様子を見てもらえ状況を伝えやすいので、同席がおすすめです。
面談の所要時間は30分くらいでした。
まず、担当者と息子が中心となり、簡単なやりとりをしながら息子の様子を確認してもらいました。
そして、後半は記入した「就学相談シート」をもとに、子どもの生活や発達状況を伝えました。

就学先検討の判断材料になるので、
普段の家庭や園での様子を正直に伝えることがポイントです。
③特別支援学級・特別支援学校の見学(保護者と本人)
面談の後日、教育委員会の担当者から特別支援学級の見学の日程の連絡がきました。

息子は「特別支援学級」のみ見学しましたが、
「特別支援学級」と「特別支援学校」の両方を見学する方もいました!
そして、7月に息子が通う予定の小学校に、息子と一緒に見学しました。
- Q特別支援学級の見学ではどんなことをするの?
- A
息子の小学校で行ったこと
- 特別支援学級での体験授業(支援級在籍のお子さんと一緒に、簡単な自己紹介や課題、絵本の読み聞かせに参加させてもらった)
- 通常学級の様子をみる(廊下から授業の様子を見させてもらった)
- 校長先生や特別支援教育コーディネーターとの面談(支援学級の状況を聞いたり気になることを質問)
実際にクラスの雰囲気や先生方の対応を見ることで、現実的なイメージができました。
学校によって支援学級の雰囲気は違うので、お子さんが通う予定の小学校へ見学に行くことはおすすめです。
④就学先の希望を伝える(保護者)
見学や面談を経て、保護者が希望する就学先を教育委員会に伝えます。
「通常級でがんばらせたい」「まずは支援級でサポートを受けたい」など、家庭によって考え方は様々だと思います。
わが家は夫婦で意見が分かれていたので、就学先の決断には苦労しましたが、何度も話し合って決めました。
⑤保育園・幼稚園・認定こども園などへ訪問(教育委員会担当者のみ)
教育委員会の担当者が、息子が通っている園を訪問して、活動中の息子の様子をみたり、先生から園での様子についての話を聞きます。
日常的に息子を見ている第三者の意見が加わることで、より客観的な判断材料になります。
⑥就学時健康診断の受診及び小学校との教育相談会(保護者と本人)
秋ごろになると、各小学校で就学時健康診断があります。
息子の通う小学校では、身体測定や視力・聴力検査など一般的な内容に加え、簡単な発達検査も行われました。
そして、健康診断の後に、小学校の先生との教育相談会がありました。
教育相談会は、希望者のみで親子1組ずつ順番で行われました。
これまでに、面談や見学など一通り参加して、伝えたいことは全て出し切っていましたが、念のため再度、「支援が必要な場面」や「入学までの準備」について確認しました。
⑦市の教育委員会による審議(教育委員会担当者のみ)
すべての情報をもとに、教育委員会で就学先についての審議が行われます。
保護者の希望・園からの意見・子どもの面談結果などを総合的に判断し、就学先が決められます。
保護者はこの場には参加できないので、待つしかありません。

希望通りの就学先になるか…少し不安でした。
⑧就学通知を受けとる(保護者)
1月ごろに、「就学通知」が届き、就学先が確定します。
わが家では「支援学級」希望で、希望通り「支援学級」の決定通知を受け取ったのでホッしました。
あとは、4月の入学に備えて入学準備を進め、心配なことや気になることがあれば学校に直接連絡します。

もし、「就学通知」が希望通りの就学先でなく、納得がいかない場合…
まずは、教育委員会に連絡し、理由を確認することが大切です。
再度、相談の場を設けてもらいましょう!
就学相談に備えて準備しておきたい持ち物リスト
就学相談は、お子さんに合った学びの場を考える大切な時間です。
当日は緊張してうまく話せなかったり、言い忘れてしまったりすることもあります。
だからこそ、事前に持ち物を整理して準備しておくことが安心につながります。

事前に準備したことや持ち物をチェックリストにまとめました!
就学相談は受けた方がいいの?メリット・デメリットを解説
就学相談を受けるかどうかは、お子さんの発達や行動、学習面などに不安がある親にとって大きな悩みどころです。
「受けたらどんな良いことがあるの?」「受けないと不利になるの?」と迷う方も多いと思います。
ここからは、実際に私が就学相談を経験して感じたメリットと、就学相談を受けなかった場合に考えられるデメリットを整理していきます。
就学相談を受けてよかった!具体的なメリットとは?
結論を言うと、私は就学相談を受けてよかったと思っています。
就学相談を受けないと後悔するかもしれないデメリット
一方で、就学相談を受けなかった場合には、次のようなリスクがあると感じています。
就学相談は受けない選択もできますが、少しでも小学校生活への心配があるなら、受けておくことをおすすめします。

入学後に「相談しておけばよかった」と後悔しないように!
就学相談で失敗したわが家の体験談|後悔しないための工夫
就学相談は、子どもの進路を左右する大切な場です。
ですが、いくら情報を集めて準備しても、後になって「こうすればよかった」と思うことは出てきます。
私自身も、実際に体験してみて後悔したことがあります。
① 夫が一度も就学相談に参加しなかった
わが家では、就学相談や小学校の見学にすべて私ひとりで参加しました。
「平日だから夫を誘っても来れないだろう」「私が参加して夫に情報を共有できればそれでいい」と思っていたからです。
子育てや学校関連のことは母である私の担当だという暗黙のルールが夫婦間でできていました。
しかし、その考えは間違っていました。
結果的に、夫が一度も就学相談に同席しなかったことで、就学先の決断をする時に夫婦で意見がもめて苦労しました。
私がどんなに説明しても上手く伝わらず、親がそろって話を聞き、同じ視点で情報を共有することの大切さを痛感しました。
② 実際に入学してみないと分からないこともある
就学相談では、学校や学級の制度や支援体制について詳しく説明してもらえます。
さらに、見学で実際に通う小学校の雰囲気を知ることもできます。
しかし、実際に子どもが入学してみて、初めて気づくことがたくさんありました。
息子が入学した年は、先生の大幅な異動時期と重なりました。
そのため、見学の時の支援級の雰囲気とはかなり違う印象を感じました。
さらに、息子が1年生の時の担任の先生は初めての支援級で、事前に就学相談で伝えた情報が全く伝わっていませんでした。
そのため、再度、担任の先生に一通り息子のことについて話しました。
「就学相談で伝えたのに!」と、イライラしてしまった時期もありましたが、どんなに相談や見学を重ねても、予測できないことはたくさんあります。
就学相談は通過点であり、すべてを就学相談で終わらせる必要はありません。
入学後も息子や学校の様子をみながら「どう支えていくか」を常に考えていくことが、親にできる最大の役割だと感じています。
まとめ|就学相談をスムーズに進めるためのポイント
就学相談は、子どもの学びの場を決める大切なプロセスです。
だからこそ、「後悔しないための工夫」を知っておくことが大切だと実感しています。
就学相談をスムーズに進めるために、次のことを意識してみてください。
「うまく話せるかな」「思い通りの結果になるかな」と不安なことはたくさんあると思いますが、就学相談は「子どもを理解してもらうための第一歩」です。
相談で得た情報を土台にしながら、入学後に子どもが安心して学べるよう、親としてサポートを続けていくことが一番のポイントです。

一人で抱え込まずに。
夫婦で、園や学校の先生と一緒に進めていきましょう!