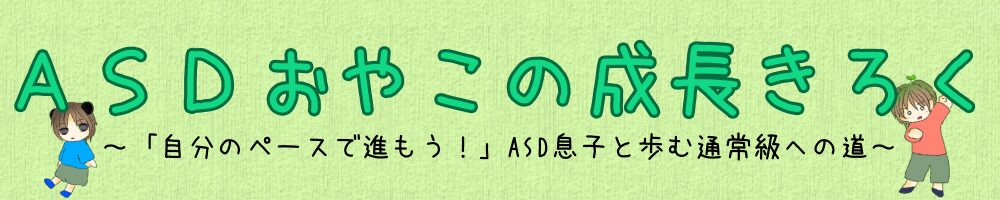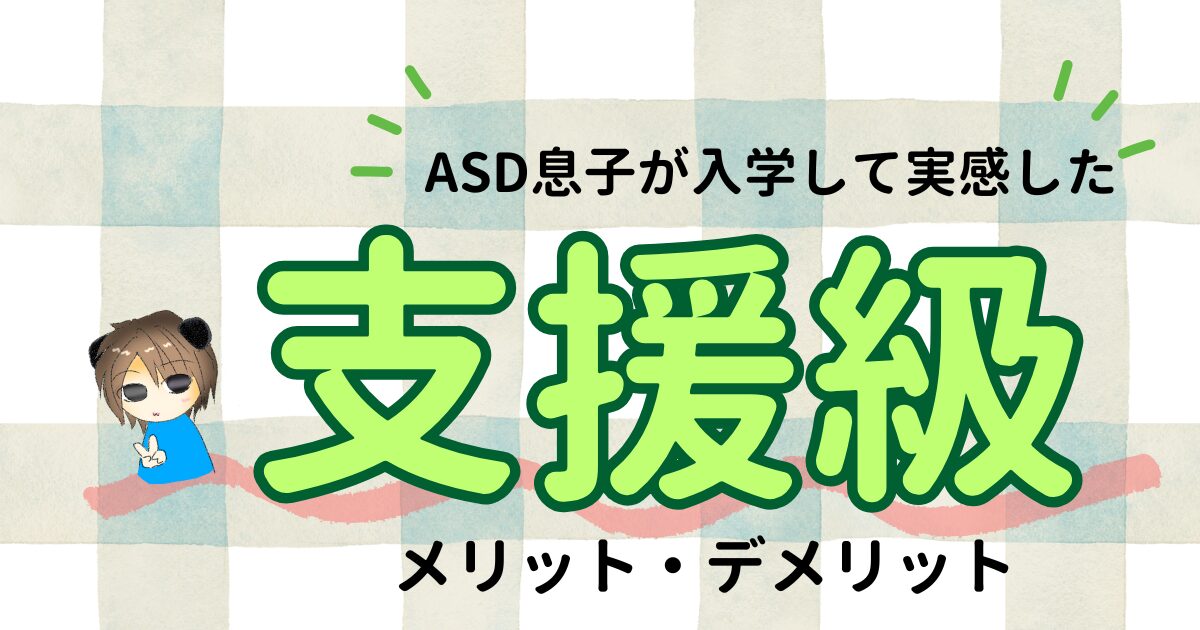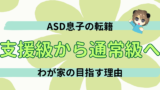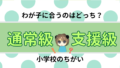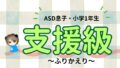わが家のASDの息子は現在小学2年生です。
入学前に「通常級」か「支援級」で、どちらが息子に合っているのかを真剣に考えました。
結果として支援級を選び、今2年目を迎えています。
この記事では、支援級にASD息子が入学して親である私が感じたメリット・デメリットをお伝えします。
就学先に悩むママやパパの参考になれば嬉しいです。
わが家が支援級を選んだ理由と入学前の不安
なぜ支援級を選んだのか
息子は3歳でASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けました。
また、幼稚園のころは、集団活動でのつまずきや、こだわりによるトラブルが多かったです。
そのため、幼稚園を2ヶ月で休園することになり、療育園に2年間親子で通いました。
幼稚園の入学時の失敗を繰り返さないために、小学校の就学先を決める就学相談では、たくさんの情報を集め、さまざまな意見を聞きました。
その上で、息子が安心して学べる環境はどこかを夫婦で話し合った結果、「支援級」の判断にたどり着きました。
入学前に心配だったこと
しかし、息子の安定のために「支援級」を選んだとはいえ、不安はたくさんありました。

小学校の生活スタイルに適応できるかな…

みんなと違った環境で不安にならないかな…

勉強はついていけるかな…
小学校入学後の息子の進路への不安
特に、「入学時は支援級でスタートする!」意志は強く持っていた私でしたが、入学後はどうやって息子を導いていけばよいのか、私自身に迷いがありました。

通常級へは転籍した方がいいのか?
転籍は何年生がいいのかな?
小学校の先生と上手く連携できるかどうか
また、小学校の先生と連携を取りながら進めていけるか自信がありませんでした。

特性が強めな息子に対して、適切な対応をしてもらえるのか。
私自身が息子のことを先生にしっかり伝えられるのか。
療育園では、息子の特性をよく理解してくれる先生がたくさんいました。
そのおかげで、息子の対応に困った時は一緒に考えてくれて、とても心強かったです。
さらに、息子が年長になって復帰した幼稚園では、ベテランの先生が担任になり、息子が園で過ごしやすい環境づくりを率先して行ってくれました。
人への興味がうすい息子が自分からアピールしに行く程、幼稚園の先生が大好きでした。
また、幼稚園の送り迎えの時に先生と毎日話す機会もあり、息子の様子を詳しく知ることもできました。
このように、療育園や幼稚園の先生達が親身に寄り添ってくれたおかげで、安心して通うことができたと思います。
しかし、小学校の先生は勉強を教えるのが仕事で、発達障害に関する知識が少ない先生が多いと周りから聞いていたので、不安がありました。
支援級スタートで実感したメリット
入学前は「本当に支援級でよかったのか」と悩んだり、不安が尽きることはありませんでした。
けれども、いざ支援級での生活が始まってみると、息子にとっても、そして親にとってもプラスに感じられることがたくさんありました。
①少人数で手厚い指導を受けられる
息子の支援級では、1クラスに入れるのは8人までで、同じクラスに1年生から6年生までの学年の子が在籍しています。
少人数で先生が息子の様子をしっかり見てくれるため、圧倒的な安心感があります。
さらに、困ったときにすぐにフォローしてもらえるので、入学してからこれまでに大きなトラブルはなく支援級で過ごせています。
②息子のペースに合わせた学習ができる
言葉の遅れがあり、国語が大の苦手な息子。
特に、読解問題や感想文は家庭で教えても全く響かず、困り果てています。
息子の小学校では、教科書にたくさん線を引きながら息子のペースに合わせて教えてくれたり、自立活動の時間に苦手な国語の問題を中心に取り組んでくれています。

もし、「通常級」だったら、みんなと同じスピードについていけずに分からないままになっていたかも…。
苦手な部分をしっかり見てくれて、学習面においても安心な環境です。
③交流の制度によって、通常級の環境で学べる時間がある
息子の通う学校では、支援級に在籍の子どもが通常級で授業を受けられる交流の制度があります。

支援級在籍の子どもが「通常級」で学ぶ時に、
「通常級」のことを「交流級」と呼んでいます。
交流級で過ごす時間があるおかげで、通常級の同学年の子と関わる機会が得られます。
息子の場合は、入学時に、支援級のクラスと交流級のクラスの発表がありました。
そのため、息子は支援級のクラス番号と交流級で授業を受けるための通常級のクラス番号があります。
ちなみに、娘が入学した数年前は、支援級在籍の子どもは交流級となる通常級のクラス名簿の一番後ろに名前が記載されていました。

「支援級の子」が分けられていて、少し気になっていました…
しかし、息子が入学した年には支援級在籍でも50音順で通常級の名簿に記載されていました。

支援級の息子もクラスの一員のように感じて、嬉しかったです!
学校によっては、まだ名簿がわかれている所もあるようですが…。
年々、多様な学びの環境の整備が進められているように感じます。
④担任や補助の先生との距離が近く相談しやすい
小学校の支援級は先生との距離がとても近く、日々の小さな困りごとでも相談しやすいです。

入学前は心配でしたが、どの先生も優しく、相談しやすい環境で助かっています。
特に、1年生のうちは支援級の教室まで送り迎えをしていたので、先生と顔を合わせる機会が多く、ささいなことでも気になったことは話していました。
現在は、登下校の付き添いは途中までになり、学校に行く機会は減りましたが、連絡帳でやりとりをしたり、たまに先生から電話がかかってきて学校の様子を教えてくれることもあります。
また、交流級へは補助の先生がメインでついてきてくれるので、学校に立ち寄った時に、補助の先生に交流級での息子の様子を聞くと詳しく教えてくれます。
支援級に入って苦労したデメリット
支援級に入って、大きな安心感や手厚いサポートがあることを実感しています。
息子に合った環境で学べることで、親としても安心できる場面が多いです。
しかし一方で、実際に通ってみて気づいた「大変さ」や「想定外の課題」もありました。
①学校や先生によって支援級の環境は大きくちがう
学校による支援級の体制のちがい
同じ「支援級」といっても、地域差・学校差が大きいです。
特に、他の小学校に通う支援級のママ友に支援級の様子を聞くと、いつも実感します。

同じ自治体でも、学校によって全然違うんだな…
例えば、交流級の時間が多い学校もあれば、支援級中心で進める学校もあります。
さらに、「情緒クラス」「知的クラス」が整っている学校もあれば、形式上だけの「情緒クラス」「知的クラス」で実態は一緒に授業を行っている学校もあります。

就学相談で小学校の見学をしたり、直接先生に聞いてみるなどして、事前に情報を集めておくと安心です。
先生によって支援級の雰囲気が変わる
支援級だけでなく通常級でも言えますが、担任の先生の経験や考え方によってクラスの雰囲気は全然ちがいます。
息子が入学した時は、先生の大幅な異動時期と重なり、見学の時の支援級の雰囲気とはかなり違う印象を感じました。
さらに、息子の支援級1年目は支援級を初めて担当する先生にあたり、お互いに勝手がわからず情報共有に苦労しました。
心なしかクラスも荒れ気味だった気がします。
しかし、2年目の今は支援級経験ありの頼れる先生に出会え、クラス全体の雰囲気が良くなり、息子自身も落ち着いて過ごせています。
先生によって、支援級の雰囲気や息子の安定感は大きく左右されると実感しました。
②「通常級と違う」ことを意識する場面がある
学習進度の差が気になる
息子の小学校では、「情緒クラス」と「知的クラス」が混在しています。
そのためか、通常級と比べると宿題の量や学習内容が少なめな印象です。
さらに、国語や算数などの授業数も少なく、音楽や体育が多めです。
そのため、「同じ学年なのに、勉強が遅れているのでは…」と不安になる瞬間もあります。
また、わが家の場合は、通常級への転籍を視野に入れているので、通常級のスピードに追いつけるのか心配でした。
ただし、他の小学校に通う支援級ママの情報によると…。
「情緒クラス」と「知的クラス」の環境が整っている学校では、「情緒クラス」は通常級と同じ学習スピードで宿題の量も変わらないそうです。

学校によっては心配不要かも…
周囲から支援級について聞かれた時
1年生のころは学校まで付き添って送り迎えをしていました。
また、支援級の教室は1年生のクラスのとなりでした。
そのためか、同じ1年生の子ども達や通学団の子ども達から、「支援級でしょ?」「なんで支援級なの?」とよく聞かれることがありました。
無邪気な質問ではあるものの、親としてどう答えればいいのか悩みました。
また、保護者の方から直接聞かれることはありませんでしたが、どこか距離を置かれているように感じることがありました。
一方で、「どこまで踏み込んでいいのか」といった空気感を察して、私から距離を取ってしまうこともありました。
特に入学直後はこうした場面に多く直面して戸惑いましたが、必要に応じて説明し、不要な時はかわしながら、深く考えすぎないようにしています。
③主体的に先生に働きかける必要がある
支援級に通ってみて感じたのは、「先生に任せきりでは上手くいかない」ということです。
支援級には一人ひとり特性の異なる子どもが在籍しており、学習の目標やサポートの方向性もそれぞれ違います。
もちろん、先生方は一生懸命関わってくださいますが、必ずしも発達障害に詳しいとは限りません。
また、家庭ごとに「どんな力を育てたいのか」「どんな支援が合っているのか」という方針も違います。
だからこそ、親が主体的に先生に働きかけることが大切だと実感しました。
例えば、子どもの困りごとや効果的だった対応方法を具体的に伝えたり、家庭での様子を共有したりすることで、より適切な支援につながります。
支援級は、先生と親が一緒に試行錯誤していく場だと思います。
子どもの成長に合わせて支援を続けていくには、家庭と学校の協力が欠かせないと感じています。

普段の授業を実際に見させてもらったり、学校ボランティアに参加するなど、
自分ができる範囲でサポートをしています。
④中学校以降の進路イメージを持っておく
支援級の最初の個人懇談会で「中学校の進路」について先生から聞かれて、「入学したばかりなのに、もう卒業後のことを考えないといけないの?」と焦りました。

まだ息子は小学1年生で小学校生活にも慣れていない状況で、先のことまで考えられない…
通常級に通う場合は、基本的に地域の公立中学校に進むか、私立中学校を受験するか、進路がある程度決まるため、小学校入学時点で詳しく聞かれることはありません。
一方で支援級では、地域の中学校の通常級へ進むか、中学校の支援級へ進むか、特別支援学校を選ぶか、私立中学校を受験するか…など。
進路の幅が広く、早い段階から方向性を考えておく必要があります。
進路によって小学校の間に転籍を検討した方がよい場合もあるため、先生方も早めに確認しているのかもしれません。
「まだ先のことだから」と思いがちですが、早くから大まかなイメージを持っておくことで、必要な準備や支援をしやすくなります。
支援級に息子を通わせて感じた母の本音

息子が支援級2年目を迎えた私の気持ちをまとめました!
安心と不安の両方の気持ちが混在する
支援級に息子を通わせて良かったと思う反面、通常級との差や今後の進路への不安は常にあります。
「安心と不安が半分ずつ」というのが本音です。
支援級に通い始めて、まず感じたのは「安心」でした。
少人数の環境で先生の目が届きやすく、息子が落ち着いて学べている姿を見ると、支援級を選んでよかったと感じます。
入学して間もないころの息子は、休み時間は「情緒クラス」の教室から1歩も出ず、1人でいることが多かったです。
ですが、次第に担任や補助の先生に息子から話しかけることが増え、支援級のクラスの子たちとの関わりも増えてきました。
息子のできることが増えていく様子を日々感じられ、とてもうれしく思います。
一方で、学年が上がるにつれ学習内容が難しくなる心配や、通常級への転籍の不安、さらに中学校以降の進路に対するプレッシャー…など、悩むことも常にあります。
安心と不安の間で揺れ動きながら、「息子にはどんな支援が必要なのか」「息子に合う学びの場所はどこか」を考えながら、日々を過ごしています。
「支援級」を選択したことに後悔はない
とはいえ、息子にとって支援級の環境が合っているのは間違いありません。
少人数で安心できる環境で自分のペースで成長させてもらえ、とてもありがたいです。
支援級に入って2年目を迎え、振り返ってみても「支援級の選択は間違っていなかった」と思っています。
もちろん、通常級を選択して得られた経験もたくさんあったかもしれません。
けれど、それ以上に「息子が自分のペースで成長している実感」や「先生に相談できる安心感」は、私の中で大きな支えになっています。
まとめ|支援級はわが子に合っていたのか
支援級に入ってみて、「やっぱりよかったな」と思えることもあれば、「ちょっと大変だな」と感じることもありました。
正直、すべてが順風満帆というわけではないけれど、息子が笑顔で学校に通えている姿を見ると「今の環境が合っているんだな」と実感できます。
子どもによって性格や特性は一人ひとり違うので、必ずしも支援級が正解とは限りません。
でも、「どんな環境がわが子には合っているかな?」と考えながら選んだ道なら、きっと間違いではないはずです。
わが家にとって支援級は、息子が自分らしく成長していける場所でした。
そして、親である私も一緒に学び、先生と支え合っていける環境だと感じています。
わが家の体験が、迷っているご家庭の判断材料のひとつになれば嬉しいです。