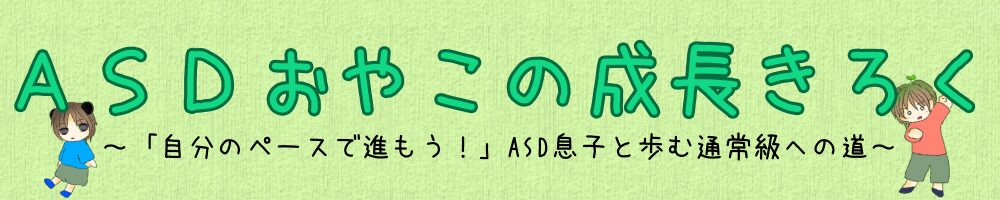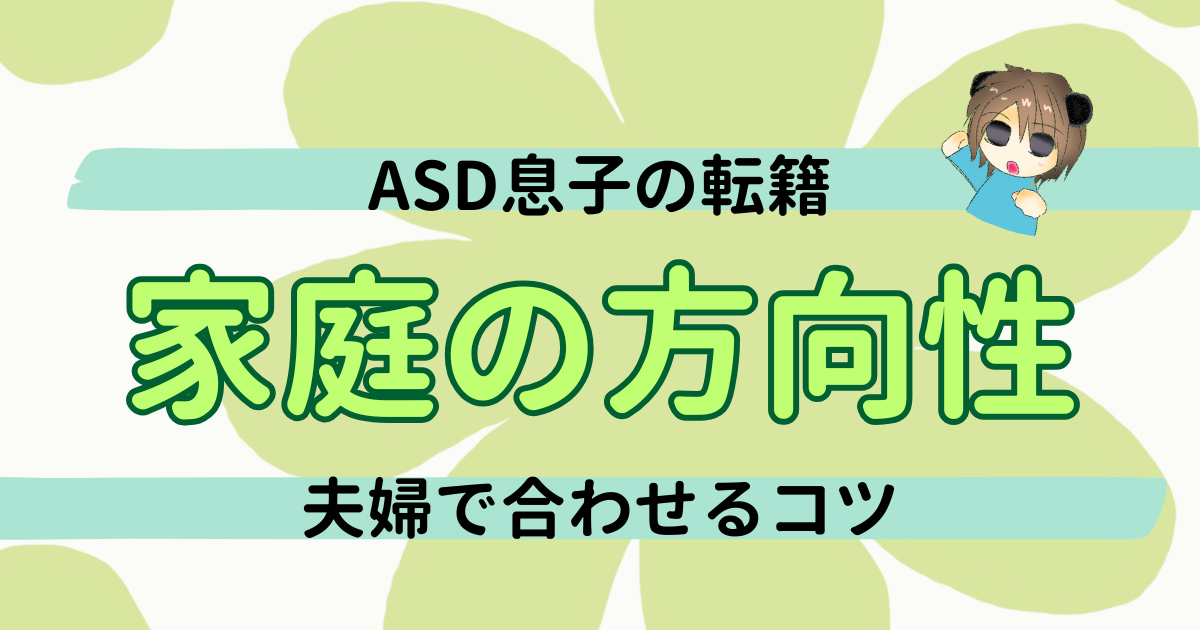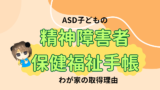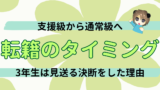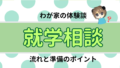こんにちは!ふたハです。
私には、小学2年生で支援級在籍のASDの息子がいます。

支援級から通常級への転籍を目指して奮闘中です!
さて、支援級から通常級への転籍に関して、私自身が一番悩んだのは「夫婦で意見が合わない」ことでした。
私は「息子の気持ちを優先してゆっくり進めたい」と慎重に考える一方で、夫は「息子の将来のために早く挑戦させたい」と前向きな気持ちを強く持っていて…。
お互いの思いがぶつかり合い、話し合うたびに疲れてしまうこともありました。

「子どものために!」と、同じ思いなのになかなか歩調がそろわない…
この記事では、わが家が実際に経験した通常級転籍に対する夫婦のすれ違いと夫婦で対立した時の解決の手段をまとめています。
ASD息子の通常級転籍で直面した悩みと夫婦の対立
息子が小学校に通い始めてから、私たち夫婦の間で「転籍のタイミング」をめぐって意見が分かれるようになりました。
「まだ早いのでは?」不安が強い慎重派の母
私は「支援級でしっかり力をつけて、息子の気持ちに寄り添いながら転籍を進めたい」と考えていました。
少人数で先生の目が行き届き、安心して学校生活を送れる支援級の環境。
息子にはとても合っていると感じていました。
入学してしばらくは、「早く環境に慣れて、のびのび楽しく学校生活を過ごしてほしい」
それが、私の一番の願いでした。
また、息子のペースで少人数で手厚く教えてもらった方が、息子の力が伸びるのでは…?
…とも思っていました。
もし、通常級で過ごすとなると、授業のスピードや集団行動への参加など、息子にとって大きな負担が増えることが予想されます。
「授業についていけなかったら?」「友だち関係でつまずいたら?」と不安ばかりが膨らみ、早い段階での転籍には踏み切れずにいました。
「挑戦させたい!」気持ちが強い積極的な父
一方で、夫は「通常級の環境に早めに慣れさせたほうがいい」と考えていました。
将来の自立を見据えるなら、友だちと一緒に過ごす時間や、より多様な刺激を受けられる通常級での学びが必要だというのです。
「支援級の環境があたりまえになって、伸びるチャンスを逃してしまう!」
「多少つまずいても、集団の中で経験することが一番の学びになる!」
…と、よく夫は言っていました。
私が不安を口にするたびに、「失敗してもいいから、挑戦させることが大切」だと、終始一貫した姿勢で言葉を返してくる夫。
息子の可能性を広げるために、少しでも早いタイミングでの通常級への転籍を希望していました。
すれ違いが続いたことですり減る気持ち
しかし、意見がなかなかまとまらず、次第に夫の言葉をプレッシャーに感じるように…。
お互いに息子のためを思っているのに、歩み寄れないもどかしさが募っていきました。

どうして私の気持ちを分かってくれないの?
話し合いをする度に、険悪な雰囲気になり、話し合いは平行線のまま。
夫婦関係そのものが揺らいでしまいそうになる程、不安に感じる日もありました。

私が折れて夫に意見を合わせれば…
こんな思いをしなくても済むのかな…
重たい気持ちに耐えられず、夫と話し合うことから逃げたくなった時期もありました。
夫婦で意見が合わない原因とは?夫に現状を知ってもらう工夫
夫婦で意見がすれ違う中で、息子に対する私と夫の距離感を強く感じました。
私は息子と接する機会が多いので、日常の中での息子の苦手さや困り事にささいなことでもすぐ気づけます。
でも、仕事で忙しい夫は、息子の困り具合を実感できていませんでした。
さらに、息子は慣れている相手に向けて困り事をぶつけてくるので、私は息子の対応が大変だった経験がたくさんあります。
一方で、息子との距離が遠い夫は、息子の対応に苦労した経験が少ないです。
そこで、感情だけでぶつかり合うのではなく、夫に息子の現状を理解してもらうためにはどうしたらよいかを考えました。

私が実際に取り組んだ方法を紹介します!
息子の「今の力量」を数値で示す
まず、数値やデータで息子の現在地を可視化する方法を紹介します。
感情や主観だけで話すと、どうしても平行線になりがちです。

数値やデータを共有して、少しでも夫婦の認識のズレを埋めよう!
①発達検査を受けて、学習や生活面の得意・苦手を明確にする
発達検査にはいろいろな種類がありますが、通常級への転籍を検討するにあたり、今回息子が受けたのは「WISC-V知能検査」です。
「WISC-V知能検査」とは
5歳0ヶ月~16歳11ヵ月の子どもの知能を測定する固定式の検査であり、10の主要下位検査を実施することで、全体的な知能を表すFSIQと、5つの主要指標得点(VCI、VSI、FRI、WMI、PSI)を算出します。
また、必要に応じて二次下位検査を実施し、補助指標得点を算出します。
それらの得点や得点のバランスから、お子さんが「同年齢の子ども達と比べてどのくらいの力を持っているか」や、お子さんの「苦手なこと」「得意なこと」が分かるようになっています。
お子さんの特徴についての理解を深め、日常生活や社会的支援のより効果的な方法を工夫する、サポートの指標として活用されています。
「WISC-V知能検査」で分かった息子の力量
息子の「WISC-V知能検査」の結果をみると、全体的な知的発達水準「FSIQ」は「平均の下~平均の数値でした。
別の発達検査ですが、就学前は軽度知的~境界知能数値だったので、今回の数値は私が想定していたよりも高かったです。
しかし、各指標ごとに見ていくと数値に差があり、得意なことと苦手なことのバラつきが大きいところが気になりました。
特に、「VCI」(言語理解指標)と「WMI」(ワーキングメモリ指標)が低く、言葉の苦手さと覚えられる量が少ない課題があることが分かりました。
そして、「WISC-V知能検査」の結果を夫に見せながら、息子の苦手な部分や必要な支援について説明しました。

私自身も息子の得意・不得意を再認識でき、新たな発見もありました。
「WISC-V知能検査」を受けてよかったです!
②障害者手帳を取得して、日常生活の困り具合を伝える
また、精神障害者保健福祉手帳の取得も、「息子には支援が必要だ!」と夫に伝える有効的な手段の一つになりました。
精神障害者保健福祉手帳とは…「障害者手帳」のうちの一つ
障害者手帳について
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
精神障害者保健福祉手帳を息子が取得した経緯
息子が小学1年生の時に精神障害者保健福祉手帳を取得しました。
もともと、息子が4歳の時に療育手帳を取得していましたが、2年後の手帳の更新で数値が基準値を少し上回り、6歳の時に返納することになりました。
しかし、知能指数が上がったからといって、息子のASDの特性が改善されたわけではありません。

療育手帳を返納する時にとても不安を感じました…
そんな時、療育手帳の更新で発達検査を担当してくれた方が、息子の特性の強さを心配してくれ、精神障害者保健福祉手帳の取得をすすめてくれました。
これが、精神障害者保健福祉手帳取得のきっかけになりました。
精神障害者保健福祉手帳で「2級」判定だった息子
息子が2、3歳くらいのころと比べると育てやすくなっており、夫もずっと「息子は軽度だ!」と言っていたので、息子の自閉スペクトラム症の程度は軽いものだと思い込んでいました。
さらに、療育手帳の知的障害の判定も軽度でしたので、精神障害者保健福祉手帳も3級で交付されるだろう考えていました。
しかし、結果は「2級」で想定よりも重たい判定でした。
息子がASD(自閉スペクトラム症)であることの受容はできているつもりでしたが、正直ショックでした。
とはいえ、夫に息子の困り事の大変さを知ってもらえる効果としてはとても大きかったです。
私自身も、息子のASD(自閉スペクトラム症)の特性の強さを再認識することができました。

精神障害者保健福祉手帳を持っていると
たくさんの福祉サービスを受けられます!
息子の学校での様子を具体的に伝える
家庭の様子だけを見ていると、「やりとりができるようになってきた」「宿題にも毎日取り組めている」「特に大きなトラブルがない」ため、特に問題はないのでは…と夫は感じていたようです。
けれど、学校生活には家庭では見えない一面がたくさんあります。
①夫に学校の連絡帳を見せる
夫は仕事の忙しさを理由に、子育ては私に任せっきりで、学校や先生と直接関わる機会が少ないです。
そのため、息子が学校でどんな様子で過ごしているのか、分かりにくい立場にありました。
そこで私は、担任の先生とやりとりをしている連絡帳をそのまま夫に見せることにしました。
良かったことも困ったことも先生の言葉で記録されているので、私が説明するよりも、学校での息子の様子が夫に伝わりやすいです。
②個人懇談会に参加できない夫への対応
また、学校では、年に数回、担任の先生と1対1で話せる個人懇談会があります。
息子の通う学校では、通常級では1人10分しか時間がありませんが、支援級では1人1時間くらい時間をもらえるので、ゆっくり話をすることができます。
ただ、平日に実施されるため仕事を休めず、夫が参加したことは1度もありません。
ですが、事前に夫から先生に聞きたいことをヒヤリングして、先生に伝えるようにしています。
そして、個人懇談会での先生の言葉を忘れないようにメモをとりながら聞いて、夫にフィードバックしています。
③夫が学校の様子を見る機会をたくさんつくる
さらに、夫自身が 直接学校での息子の姿を見られるように、積極的に学校の行事に誘うようにしました。
今までは、「仕事が忙しくて、どうせ休めないだろう…」「仕事で大変だから土日はゆっくりしたいかな…」「誘って文句を言われたら嫌だな…」など、夫に気を遣っていました。
でも、私が話すよりも実際に直接夫の目で見た方が、息子の現状をより鮮明に伝えることができます。

夫と一緒に参加して、授業中の様子や友だちとの関わりを見てもらおう!
専門家の意見を共有する
ただ、家庭や学校の様子だけでは判断が難しい部分があります。
また、私がどんなに説明しても、夫には「心配しすぎ!」だと真剣に受け止めてくれないことも多かったです。
そこで役立ったのが、専門家の意見です。
①夫に最も効果のある「主治医」の意見
特に、息子の発達をずっと診てもらっている主治医の言葉は夫に響きました。
主治医は息子の転籍には慎重派なので、私にとっては大きな戦力です。
主治医に通常級への転籍の話をすると、難色を示しながら「息子や学校の状況を見ながら判断した方がよい」「現状の息子のやりとりレベルでは難しいのでは…」とはっきり言ってくれ、そのまま主治医の言葉を夫に伝えました。
私の感情的な意見よりも主治医の客観的な意見の方が、夫には冷静に受け止められるようでした。
②夫が耳を傾けやすい第三者の意見
また、学校の先生や放課後デイサービスの職員などの「現場で直接息子と関わっている人の声」も夫はよく聞いてくれます。
そのため、母親からの一方的な情報ではなく、複数の立場の人の意見をたくさん集めて夫に伝えるようにしています。
夫婦で話し合いを重ねる中で見えてきたこと
息子の通常級への転籍をめぐって、夫婦で何度も話し合いを重ねてきました。
最初は意見がかみ合わず、正直「どうして分かってくれないの?」と感情的になることも多かったです。
ですが、時間をかけて対話を続けたことで、少しずつお互いの考えや想いが見えてきました。
夫の意見が全く理解できなかった話し合い初期のころ
転籍の話し合いの初めのころは、私は夫の「挑戦させたい」という意見に強い抵抗感を抱いていました。

世間体が気になるだけでは…?
「やればできる」の根性論ではムリ!
「無理をして息子がつまずいたらどうするの?」「最終的に対応するのは私だから無責任なこと言わないで!」と夫に対して不信感でいっぱいでした。
夫の言葉はどれも「現実を見ていない」ように感じました。
母が共感した夫の通常級への想い
しかし、話し合いを続けるうちに、夫の「息子の可能性を信じたい」「できることを増やしてあげたい」という想いに触れることができました。
特に、「息子が将来自分の力で生きていけるように、通常級で社会性を学び、自立につながる力を少しずつ積み重ねてほしい」という夫の願いには強く共感しました。
最初は理解できなかった夫の言葉も、息子の未来を思ってのものだと気づき、少しずつ私の気持ちも和らぎました。
お互いの本音を伝え合った先に出た結論
夫と何度も意見をぶつけ合いましたが、完全に意見を合わせることは現段階でもできていません。
でも、1つ一致したことがあります。
それは、「息子が大人になった時に、自分の力で生きていけるように育てる」という目標です。
息子自身の力で仕事をして収入を得て、日常生活を自分で回せるようになってほしい。
そのためにはまず、学校生活の中で「自分で考え、行動する経験」を積むことが欠かせません。
支援級から通常級への転籍はその一歩です。
通常級での学びは、息子にとって簡単な道ではないかもしれません。
でも、挑戦の場で得られる小さな成功体験や困難を自分なりに乗り越える経験が、将来自立する力につながると信じています。
一度で結論を出さなくても大丈夫!状況に応じた目標の再設定
夫婦で話し合いを重ねる中で、「息子が大人になった時に自立できるように育てたい」という大きな目標は一致しました。
ただ、具体的に「いつ転籍するのか」という点では、すぐに結論を出すことができませんでした。
お互いの意見に寄り添い、「3年生になったら通常級へ」と一旦決めましたが、実際に息子の様子を見ていくと、もう少し準備に時間が必要だと感じる場面が多くありました。
そのため、「4年生からの転籍」にシフトすることにしました。
そのおかげで、夫婦の間のプレッシャーが減り、息子自身も落ち着いて準備を進められるようになりました。
目標を決めたら「絶対にすべき!」ものではなく、お子さんの成長に寄り添いながら見直していく必要があります。
一度立てた目標を変えるには勇気が入りますが、息子の状況に応じて柔軟に判断していくことが大切だと学びました。

息子にとって、より良い選択ができるように!
まとめ|通常級転籍で夫婦で意見が合わない時のヒント
支援級から通常級への転籍は、子どもの成長や将来を思うからこそ、夫婦の意見がすれ違いやすいです。
我が家も、転籍のタイミングをめぐってすれ違いを繰り返してきました。
しかし、数値や専門家の意見を取り入れ、息子の現状を夫と共有できる工夫を積み重ね、話し合いを続けたことで、少しずつお互いの考えを理解できるようになりました。
さらに、「将来、息子が自分の力で生きていけるように育てる!」という大きな目標で一致し、転籍のタイミングも柔軟に見直すことができました。
夫婦で意見が合わないことは決して珍しいことではありません。
一度で結論を出そうとせず、子どもの成長や状況に合わせて目標を調整していくことが大切です。
同じように「通常級への転籍」を考えているご家庭にとって、我が家の体験談が少しでも参考になり、一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しく思います。