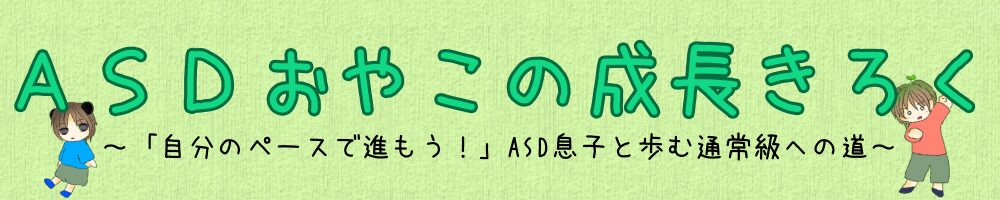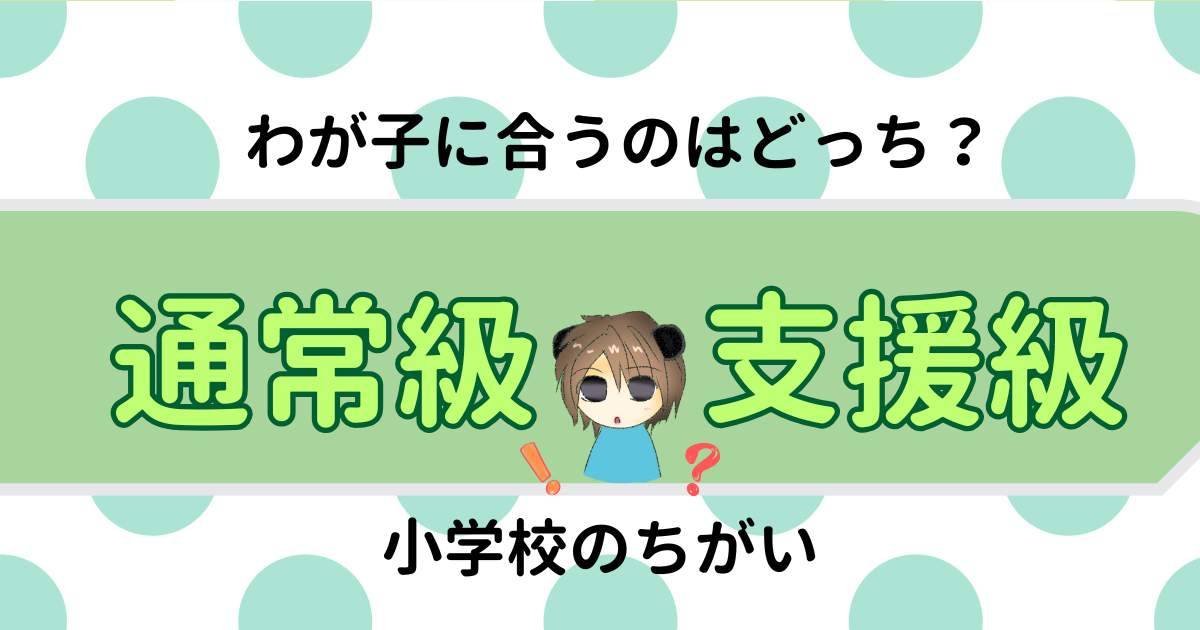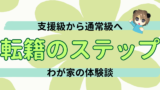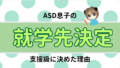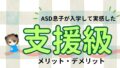わが家には、現在小学2年生のASDの息子がいます。

「通常級」と「支援級」…
息子にはどっちがいいのかな?
就学先の選択肢は「通常級」と「支援級」以外にもありますが、息子の場合は、身辺自立がある程度できていたので、わが家は地域の小学校の「通常級」か「支援級」で考えていました。
そして、就学相談を通して、息子が通う小学校の通常級や支援級の理解を深め、わが家は「支援級」に決めました。
この記事では、通常級と支援級の違いを整理するとともに、ASDのお子さんに合った環境選びのポイントをまとめていきます。
「通常級」と「支援級」の基本情報を整理
まずは、「通常級」と「支援級」がどんな学びの場であるのかを整理しましょう。

なんとなくはイメージできるけど…
具体的にはどんな違いがあるのかな?
①制度上の位置づけ
通常級(通常学級)について
支援級(支援学級)について
②対象となる子どもの範囲
通常級(通常学級)
支援級(支援学級)
③学習内容の違い
通常級(通常学級)では
支援級(支援学級)では
④サポート体制の違い
通常級(通常学級)
支援級(支援学級)
個別の教育支援計画とは?
障害のある幼児児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として策定されるもの

担任の先生と相談しながら、学習面や生活面での目標を設定しています。
学期末に、先生と一緒に進捗を確認しながら、息子の成長や課題を共有しています。
⑤学校生活の違い(人間関係・集団活動など)
通常級(通常学級)では
支援級(支援学級)では
ASD息子による「通常級」と「支援級」のメリットとデメリット
通常級と支援級の制度上の違いを整理したうえで、次は、ASDのお子さんには「どっちの環境が合うのか…?」を考えていきます。
ASDの子どものよくある特性としては次のようなものがあります。
わが家のASDの息子も、こだわりが強く、人とのコミュニケーションが苦手です。
さらに、興味の幅がせまい上に独特な感性を持ち、言葉の遅れ、いつもと違う環境や予定変更が苦手だったり…感覚過敏もあります。
ここでは、わが家のASD息子が「通常級」と「支援級」を選択した場合のそれぞれのメリットとデメリットをまとめました。
ただし、同じ自閉スペクトラム症(ASD)の診断であってもお子さんによって興味や得意・不得意、特性は違います。
そのため、症状や程度、困難さは一人ひとり異なるので、お子さんの状況を日ごろから把握しておくことが大切です。

息子の場合の一例として参考にしてくださいね。
ASD息子が「通常級」を選択した場合のメリットとデメリット
「通常級」のメリット
「通常級」のデメリット
ASD息子が「支援級」を選択した場合のメリットとデメリット
「支援級」のメリット
「支援級」のデメリット
通常級と支援級にはそれぞれの良さがあります。
お子さんの発達段階や性格、何を優先するのかをしっかり整理したうえで、どっちがいいのか考えてみましょう。
通常級と支援級における多様な学びの選択肢
また、通常級と支援級ではそれぞれに、学校での学習や生活に困難さを抱えた子どもに対する学びの場が整備されています。
通常級に在籍しながら通級指導を受けられる
「通常級」を選択した場合、通常級に在籍しながら、週に数時間だけ別室で専門的な支援を受けられる「通級」があります。
通級による指導(自閉症や情緒障害に応じた教育的対応)
通級による指導においては、各教科等の大部分の授業を通常の学級で学び、指導上の工夫や個に応じた手立て、教育における合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、一部の授業について当該の子供の障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために、自立活動の指導をしています。
例えば、自閉症のある子供については、他人との意思疎通に関わることや対人関係、社会生活への適応などの困難さを改善・克服を図る指導をしています。
「通級」のメリット
「通級」のデメリット
支援級には「情緒クラス」と「知的クラス」がある
「支援級」を選択した場合、「情緒クラス(自閉症・ADHDなど発達特性が中心の子ども)」と「知的クラス(知的発達の遅れがある子ども)」に分かれている場合があります。
ただし、学校によってはどちらのクラスも設置していない場合もあり、自治体によって呼び方や運営方法が異なります。
そのため、お住まいの自治体やお子さんが通う小学校に事前に確認しておくと安心です。
支援級の「交流」制度について
また、「支援級」には、通常級の授業や学校行事に参加できる交流があります。
この制度によって、「支援級」を選択した場合でも、通常級の友だちと自然に関わる機会を持てます。

息子の通う小学校の交流は
1年生は「図工」「体育」「音楽」「生活」など、参加しやすい教科で設定されています。
ただし、交流の頻度や内容は学校によって差があります。
よって、就学相談で実際に見学して雰囲気を確かめたり、学校の先生にどのくらい交流に行けるか直接確認することが大切です。
子どもに合う学びの環境をアップデートしていく
就学先を決めるとき、「小学校6年間ずっと同じ形で過ごす」と思いがちですが、実際には子どもの成長や環境の変化に合わせて学びの場を調整することが可能です。
一度の決断で将来を決めるのではなく、「今の子どもに合った選択」をして、その後も柔軟に見直していけることを知っておくと安心です。
「転籍」によって、入学後に学びの環境は変えられる
小学校に入学してから「やっぱり通常級では負担が大きい」「支援級で力をつけたから通常級に挑戦したい」と思うケースはたくさんあると思います。
就学先は一度決めたら終わりというわけではありません。
子どもの成長や環境の変化に応じて、教育委員会や学校と相談の上で、学級を変更することが可能です。
入学後も環境を変えられることを知っておくと、最初の選択に過度に悩まず、子どもに合った学びを実現できます。
家庭と学校と専門家の連携が大切
そして、子どもに合った学びの環境を整えるためには、家庭・学校・専門機関の連携したサポートが欠かせません。
このように複数の目で見守りながら連携を重ね、息子にとってどんな環境や支援が一番ベストなのかを日々考えています。
まとめ|通常級と支援級の違いを理解して子どもに合った選択へ
通常級と支援級には、それぞれに特徴やサポートの仕組みがあり、子どもに合う・合わないは一人ひとり異なります。
就学先を考えるときは、 通常級と支援級の違いを理解したうえで、子どもにとって安心して学べる環境はどこかを基準に判断することが大切です。
また、入学後もお子さんの成長や状況の変化に合わせて環境を見直すことは可能です。
入学前の段階で、プレッシャーを感じすぎないように「今」のお子さんに合った選択をすることもポイントです。
就学相談や学校の先生、専門機関などに相談しながら情報を集め、最終的に家族で納得ができるように、お子さんの学びの場を決めていきましょう。