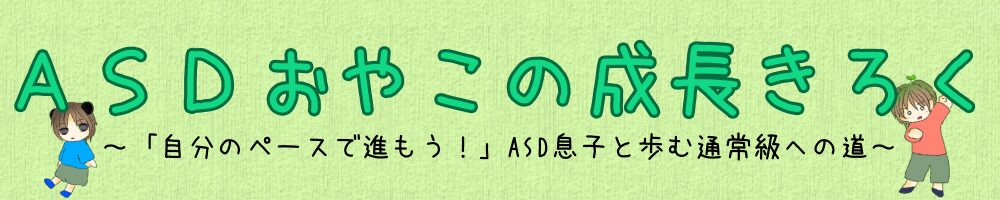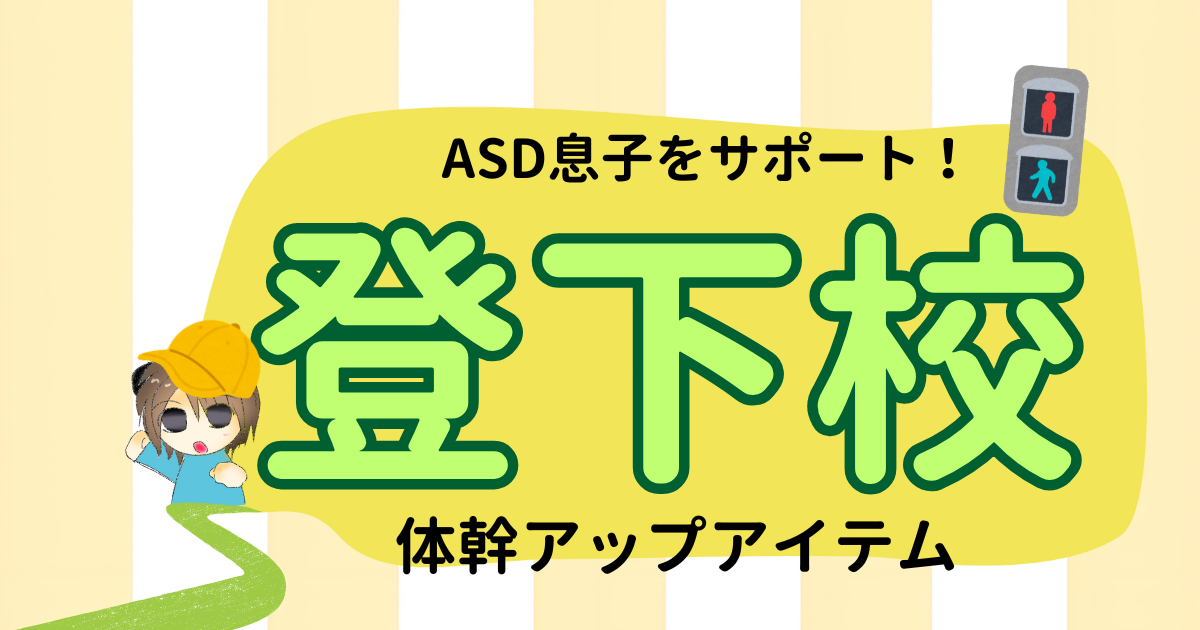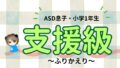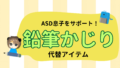わが家のASD息子が小学1年生の頃、「登下校」での困難がたくさんありました。
毎日息子の登下校に付き添う中で、特に、歩行の不安定さが気になっていました。

息子1人で学校に行けるには、どんなサポートをしてあげたらいいのかな?
そんなときに出会ったのが、作業療法士さんから教わった体幹トレーニングでした。
「体の軸を安定させることが、登下校や学習の基礎になる」と指導を受け、家庭でもできる体幹アップのアイテムを取り入れました。
その結果、小学2年生の現在では、家の近くの集合場所付近から1人で行けるようになりました。
この記事では、息子の登下校を安定させるために家庭で実践した方法を紹介します。

お子さんの登下校に悩みを抱えるママやパパへ届けます!
ASD息子の登下校で感じた課題とは?
息子が入学してから半年間は、登校時は学校まで付き添い、下校時は学校まで迎えに行く日々でした。
息子の学校では、登校時は登校班で学校に行き、下校時は学年ごとで帰宅します。
そのため、登校班や学年の子ども達のペースに合わせる必要があり、何度もつまずきそうになったり、歩道橋の上り下りで流れをとめてしまったり…

毎回ヒヤヒヤしながら付き添っていました。
ASDの特性から、体のバランス感覚や空間認知がまだ十分に育っていないこともあり、歩く、階段を上る、下りるなど、動作ひとつにも苦労がありました。
まず、息子が実際に直面した登下校での課題をふりかえります。
登校班の歩くスピードに合わせる難しさ
登校班では、上級生の歩くスピードが早く、集団のペースについて歩くのは、思っていたよりも大変で難しいです。
その状況で、前の子との間があいてしまっても気にせずに自分のペースで歩こうとする息子。
最初のうちは、私が隣で付き添い、「前を見て!」「あいてるよ!」など声かけをしたり、手をつないで一緒に歩くテンポを確認するなど、サポートしていました。
つまずいたり、転んだりすることが多い
少しの段差でもバランスを崩しやすく、つまずいたり転んだりすることが多い息子。

何でこんなところで転ぶの?
さらに、あいてしまった前の子との間をつめるために、慌てて走ることも多くて危ないです。
また、転ぶと大声で泣き叫んで、しばらく立ち直れないので、できる限り転ばないように手をつないだり、転びそうになったら支えることもありました。
歩道橋の階段の上り下りが不安定
私が一番心配だったは、家と学校の中間地点にある歩道橋です。
息子の歩行が安定するまでは、一緒に歩道橋を渡りながら「右(足)!左(足)!右!左!」と声をかけて上り下りの練習をしました。
また、列の乱れよりも安全を優先してほしかったので「ゆっくりでいいから階段に集中して!」と繰り返し伝えました。
作業療法士から教わった!体幹アップの重要性
息子が小学校入学の時期に、作業療法で箸や鉛筆の持ち方の訓練を受けていたので、登下校の悩みを作業療法士さんに相談してみました。
すると、息子の姿勢がグラグラしている様子から、体幹の弱さを指摘されました。
体幹を鍛えると「歩く・座る・書く」が安定する
ASDの子どもは、発達の特性によって体幹が弱い場合が多いです。

息子の場合は、こだわりの強さや感覚過敏があり、幼少期に遊具で遊ぶ経験が少なかったことが原因の一つにあると考えられます。
学校生活においては、45分間イスに座って授業を受けないといけません。
体幹が弱いと、姿勢を保つことが難しかったり、集中できないことにより、困ることや辛い場面が多くなってしまいます。
さらに、「箸で食べること」や「鉛筆で文字を書く」などの細かい動きにも体幹の強さは影響します。

たとえば、うまく鉛筆を持てないのは「手の力」だけの問題ではなく、姿勢を支えるための体幹が必要になります。
よって、登下校を含めた日常生活を安定させるためには、体幹を鍛えることが大切だと学びました。
「粗大運動」を鍛えることで「微細運動」の訓練に役立つ
息子が「箸が持てないこと」や「字が上手に書けないこと」を主治医の先生に相談したのが、作業療法を受けることになったきっかけでした。
ASDの子どもは、「手先の動き(微細運動)」が苦手な子が多いです。
でも実は、その前の段階である「体を大きく動かす力(粗大運動)」が十分に育っていないことが根底にあることを知りました。

息子は特定の遊具で遊べなかったり、幼稚園の運動会でのダンスや走り方に違和感がありました。
息子の体の動かし方はぎこちなく、姿勢も安定していなかったため、粗大運動と微細運動の両方を取り入れながら訓練することになりました。
粗大運動とは?
粗大運動とは、体全体を大きく使う運動のことです。
具体的には、「歩く」「立つ」「跳ぶ」「走る」「座る」など、日常生活において基礎となる動きを指します。
粗大運動によって、体幹・バランス感覚・筋力が育ち、「まっすぐ立つ」「長く座る」「安定して歩く」といった基本的な動作がスムーズになります。
微細運動とは?
微細運動とは、指先や手首などの細かい動きを使う運動のことです。
「文字を書く」「ハサミを使う」「ボタンをとめる」などの動作がこれにあたります。
家庭で実践!作業療法で使った体幹アップアイテム
また、息子が受けた作業療法は、1ヵ月に2回の40分間の訓練でした。
その短い時間の中で、作業療法士さんは息子の気持ちを優先して訓練内容を調整してくれ、無理にはやらせないスタンスでした。
そのため、その日の息子のコンディションによっては、少ししか訓練ができない日もあり、親としては物足りなく感じることもありました。
そこで、息子の作業療法の様子をよく観察して、作業療法士さんから訓練のポイントを聞いて、家庭でも訓練ができるように、体幹を鍛えられるアイテムを用意しました。
トランポリン|楽しみながらバランス力アップ
まず、1つめはトランポリンです。
作業療法開始時の息子は、バランスを崩していたり、高く飛べていなかったり、数分跳んだだけで疲れていました。
でも、続けていくうちに、まっすぐ跳べるようになり、体の軸が安定してきたように感じました。

蹴る力も強くなりました。
作業療法で使っていたのは、複数人でも乗れるもっと大きなトランポリンでしたが、家のスペースが広くないので、一般的な家庭用のトランポリンをわが家では購入しました。
遊びの延長でいつでも運動できるように、リビングの中央に置いてあります。

暑い日や雨の日など、外に出られない時にも
体を思いっきり動かせるので助かっています!
ジャングルジム・すべり台付き遊具|全身運動で体幹強化
そして、2つめはジャングルジムです。
息子の3歳上の娘が2歳の時に買った室内用のジャングルジムがあったのですが、息子が2、3歳の時は目が離せず、一旦物置に片付けてしまっていました。
作業療法で、家にあるのと同じようなジャングルジムを使って訓練をしたので、再度、しまってあったジャングルジムを出しました。
登る・くぐる・すべるといった全身運動ができるので、「遊びながら体幹を鍛える」にはピッタリです。
ただ、この時の息子は6歳で、遊具の対象年齢(2歳~5歳)を超えていました。
息子の体重が軽かったのでまだ使用できましたが…使用する際はご注意ください!
お部屋をスッキリさせたい/購入前に試してみたい方へ//
子供向け大型遊具レンタルのサブスク「いろいろ試せる」サークルトイズのサブスクなら、飽きたら交換OK!
・ジャングルジム/すべり台/ブランコなどの定番公園遊具
・豪華なおままごとセットやパズルなどの知育玩具
・鉄棒/トランポリン/ミニバスケットなどのスポーツ遊具
・0歳から使えるベビー用品まで!
家庭で体幹アップに取り組むときのポイント
作業療法で学んだことを家庭で実践してみると、「やらせるトレーニング」よりも「遊びの中で自然に鍛える」方が、ASDの息子には合っていると感じました。
ここでは、家庭で無理なく続けるためのポイントをまとめました。
無理をさせず「遊びの延長」で取り入れる
ASDの子どもにとって、無理なく続けられるのが一番のポイントです。
特に、小学生低学年のうちは遊びの延長で体を動かすのが効果的です。
ゲーム感覚で楽しめるように声をかけると、自然と継続できるのでおすすめです。
また、できたことをその都度ほめて「体を動かすと楽しい!」感覚を育てることも大切です。
毎日少しずつ継続して、長期的スパンで取り組む
体幹を鍛えるのは、すぐに結果が出るものではありません。
でも、続けていくうちに少しずつ成長が見えてきます。

「前より転ばなくなった」
「姿勢がしっかりしてきた」
小さな変化を見逃さず、長期的に見守っていくことが大切です。
家庭・学校・放課後等デイサービスで支援を連携させる
体幹アップの取り組みは、家庭だけで完結させる必要はありません。
学校や放課後等デイサービスと連携して進めるとより効果的です。
たとえば、先生に「姿勢が崩れやすい」「鉛筆のコントロールが苦手で字がきれいに書けない」などと共有しておくと、授業中のサポートにつなげてもらいやすくなります。
また、放課後等デイサービスでは理学療法士や作業療法士の資格を持った職員がいる所もあり、わが家も息子の運動面の相談にのってもらっています。
「家庭」「学校」「放課後等デイサービス」が連携することで、子どもが安心して力を発揮できる環境を整えることができます。
登下校が安定してきたASD息子の変化
家庭での取り組みを続けるうちに、少しずつ息子の登下校の様子にも変化が見られるようになりました。
また、日々の積み重ねの中で、体幹がしっかりしてきたのと同時に自信も育ってきたように感じました。
つまずく頻度が少なくなった
登下校中、バランスを崩すことが多く、ちょっとした段差でつまずいていた息子。
登校班の列に合わせて歩くのも大変でした。
しかし、トランポリンやジャングルジムで体の軸を保つ力がついてきたことで、歩行が安定して、つまずく回数がぐっと減りました。
階段の上り下りがスムーズになった
最初のころは、歩道橋の階段をスムーズに上り下りできなかった息子。
でも、体幹が安定してきたことで、足に力が入りやすくなり、階段の上り下りが少しずつできるようになってきたのを感じました。
その辺りから、私も息子から少しずつ離れ、今では1人で歩道橋の上り下りができるようになりました。
1人で行ける距離が増えた
「学校までついてきて!」とよく言っていた息子。
息子自身も1人で学校に行くのは不安そうでした。
でも、「今日はココまで!」と、通学路にある標識やお店を目印にして、息子が目標を決めて、その目標まで付き添いながら、1人で行ける距離を少しずつのばしてきました。
今では、登校班の集合場所から学校まで1人で行けるようになりました。
息子が1人で学校に行ける距離がのびる度に、「できた!」達成感が生まれ、学校生活全体への自信にもつながっています。
まとめ|登下校を支える体づくりは家庭でもできる!
登下校で心配なことがたくさんありすぎて、息子1人で登下校ができるイメージが持てず悩んだ日々もありました。
けれど、作業療法で教わった体幹トレーニングを家庭に取り入れて少しずつ継続した結果、歩行が安定し、自信をもって1人で学校に行ける距離が増えました。
体幹を鍛えることは、ただ運動能力を高めるだけでなく、「できた!」という成功体験を積み重ねることにもつながります。
家庭でのちょっとした遊びの時間が、登下校の安定だけでなく、子どもの自己肯定感を育てる大切な機会になりました。

3年生で家から学校までの距離を1人で行けるように、サポート継続中です!
遊びながら体幹づくり/成長に合わせて入れ替えられる/
サークルトイズのサブスクで大型遊具をチェック//

・おもちゃを買ってもすぐ飽きてしまいもったいないと感じている方
・お部屋のスペースをスッキリさせたい方
・購入前におもちゃを試してみたい方
・誕生日やイベントを盛り上げたい方

このような悩みを持っている方におすすめです!