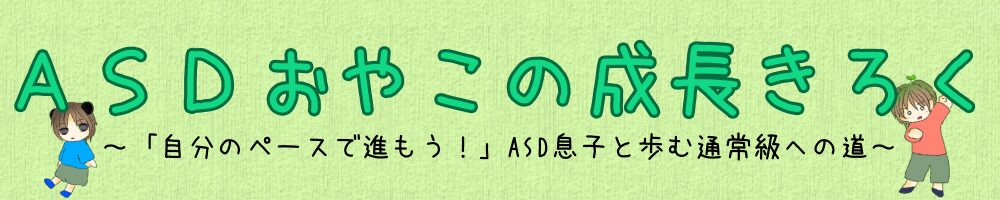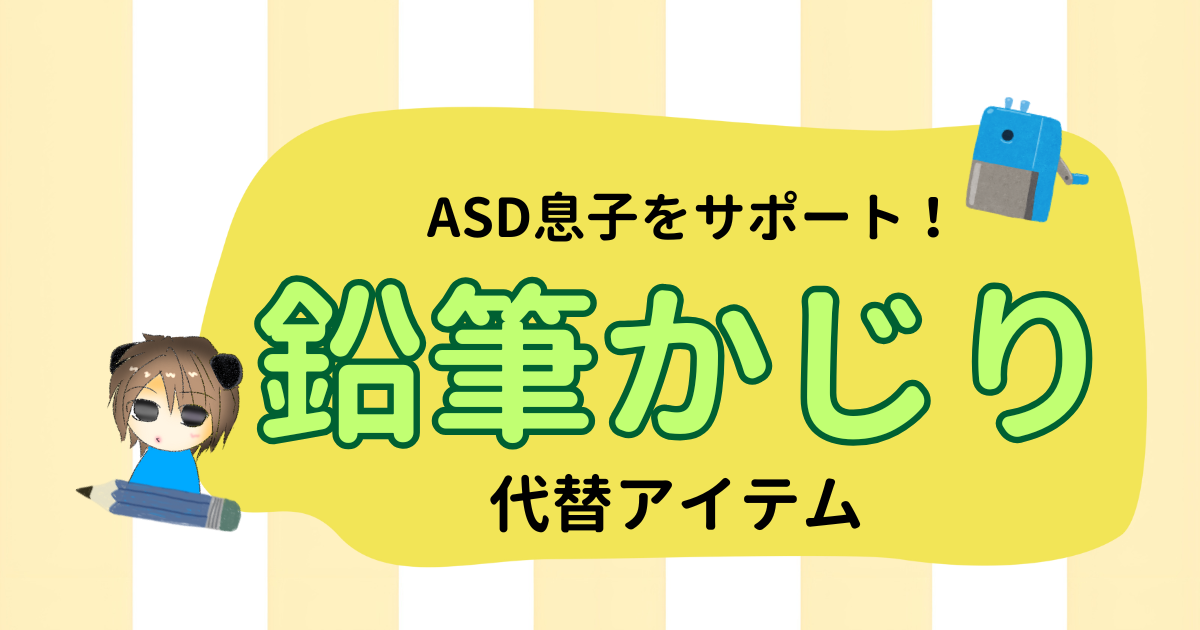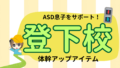授業中や宿題に取り組んでいるとき、気づくと鉛筆をカジカジ…。
「やめなさい!」と注意しても、なかなかやめられない…。

お子さんの鉛筆かじりに悩んでいませんか?
わが家のASD(自閉スペクトラム症)の息子も、小学1年生のころは鉛筆や名札、筆箱をかじってしまう時期がありました。
最初は「クセだから仕方ない」と思っていましたが、ボロボロの鉛筆を毎日見続け、見過ごせない気持ちになっていきました。
鉛筆かじりのことを調べる中で、鉛筆をかじる行動は「落ち着かせたい」「集中を保ちたい」という子ども自身の自己刺激行動の一つだということを知りました。
そのため、わが家では、叱ってやめさせるよりも、「安心してかめる環境」を整えることに注力しました。
この記事では、わが家で取り組んだ息子の鉛筆かじりの対策を紹介します。

ぜひ、お子さんに合う方法を見つけてください!
ASD息子が鉛筆をかじる理由とは?
息子が鉛筆をかむ姿を見て、最初は「クセなのか?」「ふざけているのかな?」と思っていました。
けれど、息子の主治医から話を聞くうちに、鉛筆かじりが感覚の特性や心の状態と深く関係している行動だと知りました。

子ども一人ひとりに鉛筆をかじる理由があります。
ここでは、ASDの子どもが鉛筆をかじってしまう主な原因を、感覚と心理の2つの面からお伝えします。
感覚の過敏・鈍麻による感覚行動
ASDの子どもは、触覚や味覚、口の中の感覚が敏感または鈍感な場合があります。
- 感覚が鋭いタイプの場合…退屈な時や暇な時などに好きな感覚を得るため。
- 感覚が鈍いタイプの場合…日常的な生活で受ける刺激が少なく、刺激を求めるため。
いずれにしても、鉛筆をかじることは、落ち着くために行っているのです。
不安や集中の難しさからくる行動
もうひとつの理由は、心理的な安心感を得るための行動です。
このような場面で、息子は無意識に鉛筆をかじっていました。

問題や悩みが表出しないタイプなので気づかれにくい息子。
気づかない所で悩んでいないか…心配でした。
鉛筆をかじるのは、やめさせるべき?放っておくべき?
息子が小学校1年生の6月くらいの時でした。
生活に少しずつ慣れてきた一方で、息子のつめかみや指や物をなめる頻度が増えてきました。
今思うと、これが鉛筆かじりのきっかけだったように感じます。
息子の主治医に相談し、「指摘しすぎないように」とアドバイスをもらったので、しばらく様子をみることにしました。
しかし、夏休みが明けて、運動会の練習が始まるとともに、鉛筆かじりをするようになってしまいました。
始めは、歯形がつく程度でしたが、日を追うごとにひどくなっていきました。

ピーク時は鉛筆けずりで削ったかのように、鉛筆の先端がボロボロの状態でした。
無理にやめさせることで起こるリスク

学校で頑張っているから、息子の鉛筆かじりは許容しよう…。
始めのうちは、しばらく見守っていましたが、一向に鉛筆かじりがおさまる様子は見られませんでした。
それどころが、どんどんひどくなる息子の鉛筆かじりに耐えられなくなり、私の我慢の限界が超えてしまいました。
その結果、何度も「やめなさい!」と注意してしまった時期があります。
でも、何度注意しても、息子には響きませんでした。
それどころか、やめさせようとするほど、かじる頻度が増えていきました。
また、一見「かじらなくなった=解決」と思いがちですが、無理にやめさせることで、別の行動に置き換わる可能性が高いです。
自傷行為がひどくなったり、他害に発展してしまったり…状況が悪化してしまうかもしれません。
つまり、鉛筆かじりを無理にやめさせても根本的な解決にはならないことに気づきました。
鉛筆かじりを放っておくリスク
一方で、「そのうちやめるかも」と思って放っておいた時期もありました。
しかし、毎日学校から帰ってきて、筆箱の中のボロボロの鉛筆を見る度に複雑な気持ちでした。
口に入れることで、ばい菌やトゲなどで口の中を傷つける危険性や衛生面で心配でした。
また、授業中に鉛筆を口に入れると、クラスの子から変に思われないか、息子が恥ずかしい思いをして落ち込んでしまわないか不安に思いました。
鉛筆かじりの適切な代替手段を見つける
息子の鉛筆かじりが気になっていた時期にいろんな人に相談しました。
鉛筆かじりの対策を調べる中で、ASDの子どもにとって「かじる」という行為は、落ち着くための自己刺激行動であり、鉛筆をかじる行為には息子なりの理由があることを知りました。

ちなみに、ビニールテープを鉛筆にまいてみましたが…。
自分でビニールテープをとって鉛筆をかんでしまい、
息子には効果がありませんでした。
そのため、わが家では「やめさせる」でも「放置する」でもなく、安心してかじれる代替えアイテムでサポートをすることに決めました。
実際に効果を感じた!ASD息子の鉛筆かじり対策グッズ
鉛筆かじりに悩んでいろいろ試した結果、家庭で手軽に使えて効果を感じられたのが「かじっても安心な鉛筆キャップ」でした。
ここでは、わが家で実際に試した商品を詳しく紹介します。

検討中の方は参考にしてくださいね!
かんでも安心!おすすめの鉛筆キャップ「Coollooda」レビュー
まず、1つ目は、「Coollooda」の鉛筆キャップです。
わが家で購入した商品です↓
わが家で「Coollooda」の鉛筆キャップを試した理由
メリット
デメリット/ 注意点
「Coollooda」の鉛筆キャップ|わが家での使用方法
息子愛用中!おすすめの鉛筆キャップ「かじれるくん」レビュー
次に、2つ目の「かじれるくん」の鉛筆キャップを紹介します。
シンプルなデザインで丁度良い大きさなので、学校用に使用しています。
わが家で「かじれるくん」を試した理由
メリット
デメリット/ 注意点
「かじれるくん」鉛筆キャップ|わが家の工夫
「かじれるくん」は鉛筆かじりのサポートアイテムとして早い段階で気になっていました。
しかし、価格が気になり、取り入れるまでに時間がかかりました。
また、鉛筆かじりが1番ひどい時は1週間くらいでキャップに穴があいてしまったこともあり、ショックでした。
そこで、息子と鉛筆の使用に関するルールを一緒に確認して繰り返し伝えました。
息子にとっては、落ち着くために欠かせない、サポートアイテムのひとつになりました。

鉛筆かじりがなくなった今でも、お守りとして、筆箱に入っています。
かじっても安心素材/学習中の集中サポートにも◎//
鉛筆キャップ使用後の息子の変化
かじってもいい鉛筆キャップを使い始めてから、息子の鉛筆かじりは徐々に少なくなっていきました。
そして、小学2年生の今では、ほとんど見られなくなりました。
「かじりたい衝動」を我慢せず、かみたい感覚を鉛筆キャップでしっかり満たすことができたおかげだと思います。
そして何より、「やめさせる」ではなく「思いっきりかじってOKな環境を作る」ことで、親子の気持ちがぐっと楽になりました。
息子にとっても、無理なく自然に鉛筆かじりから卒業できたのは大きな成長の一歩だったと感じています。
補足:学校対応・衛生面のQ&A
- Q誤飲や破損は?
- A
かむ力が強いと、商品に穴があいたりやぶれる頻度が多くなります。定期的にチェックをして、誤飲しないように破損したらすぐに取り換えるように気をつけています。
- Q学校は許可してくれる?
- A
支援級の担任に事前に持っていってもよいか確認しました。息子の小学校では、すんなりOKが出ました。
- Q衛生面に気をつけるには?
- A
中性洗剤で手洗い、十分に乾かすのがおすすめです。予備を用意しておくと衛生管理が楽です。また、アルコール消毒も毎日行いました。
まとめ
鉛筆をかじる行動は、ASDの子どもにとって「落ち着くための行動」であることが多いです。
無理にやめさせるよりも、安心してかじれるアイテムを使う・集中しやすい環境を整えるなど、「行動の背景」に目を向けることが大切だと感じました。
そして、鉛筆キャップを取り入れてからは、息子自身も安心して学習に向かえるようになり、結果的に集中力アップにもつながりました。
ぜひ、鉛筆かじり対策の一つとして取り入れてみてください!

お子さんの鉛筆かじりで悩んでいるママやパパの参考になったら嬉しいです。