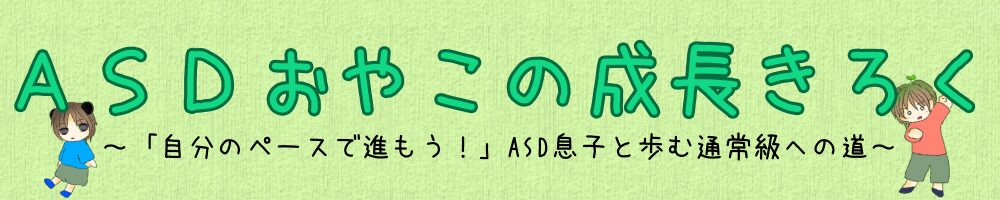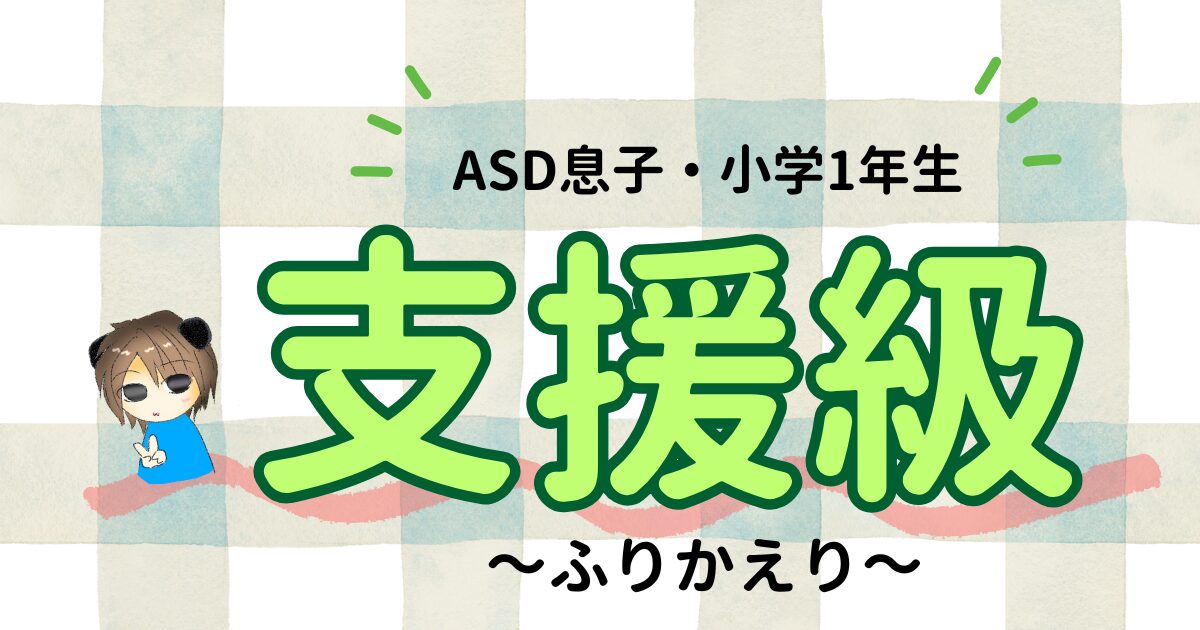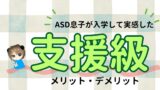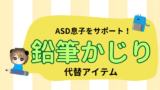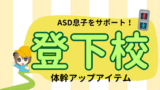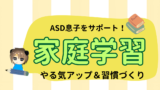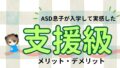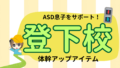こんにちは。ふたハです!
わが家のASD息子は、小学1年生から支援級に在籍しています。
息子の就学先である「支援級」については、就学前に情報をたくさん集めました。

私にとっても「支援級」は未経験の分野。
分からないことが多くて、入学前は特に不安でした。
しかし、子どもの様子や親のサポートの大変さなど、実際に支援級に通ってみないと分からないこともたくさんあります。
そこで、この記事では、支援級1年目のリアルなわが家の体験談をまとめました。
これから支援級を検討している方や、入学を控えて不安を感じている方の参考になれば嬉しいです。
支援級で1年生スタート!学校に慣れるまでの息子の困りごと
ASDの息子にとっては、環境の変化や集団行動そのものが大きなハードルです。
そのため、入学してすぐの頃は、親子共に新しい生活に慣れることを最優先にして過ごしました。

環境の変化への負担をゆるやかにするために「支援級」を選びました!
そのおかげか、大きなトラブルはなく小学校生活のスタートをきることができました。
しかし、慣れない環境下で、息子の心配なことや困った行動はいくつかありました。
支援級に入って間もないころに、担任の先生によく相談していた内容を紹介します。
困った時に先生に声をかけられない
トラブルや分からないことがあっても、自分から「先生!」と助けを求めるのが苦手な息子。
特に、慣れない場所や信頼関係ができていない相手に対しては、自分から言うことができません。
入学してしばらくの間は、先生に声をかけられず泣きそうな様子でたたずんでいることが何度もありました。
また、小学校入学時の息子は大人しく、本人が困っていることに気づかれにくいタイプでした。
その上、言葉の遅れもあったので、嫌なことがあったり上手くいかなかった時に、言葉で表現できずに自分の中でため込んでしまわないか心配でした。
そこで、担任の先生に「息子が自分で伝えるのが難しいこと」や「悲しそうな顔をしている時は困っているサイン」であることを伝え、声かけをお願いしました。

毎日、登下校の付き添いで学校に行っていたので、直接先生に伝えたり、
言葉で上手く説明できない時は、連絡帳に書いていました。
少人数でサポートが手厚い支援級の環境のおかげで、息子自身で伝えられなくても担任や補助の先生が気づいてくれて、安心して過ごせるようになっていきました。
しかし、通常級を目指すためには、自分の力で伝えらる力が必要です。

今は、言葉で伝える方法を具体的に教えてもらいながら、
自分で言えるように経験を積んでいます。
プリントや教科書への勝手な書き込み
配られたプリントや教科書に、不必要な線や数字を勝手に書き込んでしまうことがよくありました。
そのきっかけは、家庭学習にありました。
家庭学習で、視覚優位である息子に分かりやすいように、蛍光ペンで注目してほしい部分にラインを引いたり、分かりやすいように順番を書き込みながら教えていました。
「視覚優位」とは、耳から入ってくる情報よりも、目から入ってくる情報の方が処理をしやすい特性のことです。
参考資料:視覚優位・聴覚優位とは?特徴や子どもの困りごとと対処法を解説します
問題を解くよりも、線を引くことや数字を書くことが気に入ってしまい、学校の課題でも提出する宿題にも「書き込み」がやめられない「こだわり」になってしまいました。
無理に「こだわり」をやめさせると、後々問題が大きくなる傾向があったので、先生に状況を説明して、対応を一緒に考えました。
「叱られる=学校は嫌な場所」というイメージにつながらないように、学校でも家庭でも伝える頻度や声かけの仕方に気をつけながら、少しずつ繰り返し丁寧に伝えました。
クラスの子の持ち物を持ち帰ってくる
自分の持ち物への意識が低く、ランドセルや筆箱の中を確認すると、同じ支援級のクラスの子の持ち物がよく入っていました。
鉛筆や消しゴム、時には、友だちのテストが入っていたことも…。

明らかに柄が違ったり、自分以外の名前が大きく書いてあるのに。
なぜ、気にならないのか?
学校に慣れるだけでも大変で余裕がなかったのか、持ち物への興味関心が低く気づかないのか、理由ははっきり分かりません。
その都度、息子に間違って入っていることを一緒に確認して、返すように伝えました。
先生にも口頭または連絡帳で伝えて確実に返せるように対応しました。
支援級・小学1年生|息子の気になった生活面の課題
学校生活に少しずつ慣れてきた頃、分からないことを先生に聞けるようになったり、プリントへの書き込みも少なくなってきて、息子に余裕が出てきたように感じました。
しかし、その辺りから、別の気になる行動や問題が見えてくるようになりました。
登下校中や休み時間に1人でいることが多い
登下校の付き添い時や学校の用事のついでに支援級に立ち寄った時に、友だちと話したり遊んでいる様子を全く見ることができませんでした。
もともと、友だちへの興味はうすく、こだわりが強い息子。
そのため、友だちと一緒に遊ぶことは難しいと分かっており、仕方ないとは思うものの、息子がポツンと1人で過ごしている様子を見ると辛く感じる瞬間もありました。
つめかみ・指しゃぶり・物をなめる行動がやめられない
これまでも、つめかみ・指や物をなめることはありましたが、頻度が増えてきたことが気になっていました。

学校で頑張っている反動かな…?
自己刺激行動とは、感覚的な刺激を自分自身で得るために繰り返し行う行動のことです。ASDの子どもに多く見られる行動で、「感覚過敏・鈍感の特性から感覚の調整のため」「同じ行動を繰り返すことで安心感を得られるため」に行っていると考えられています。

息子が療育園や幼稚園の頃によくやっていた、自分の顔の前で手をひらひらさせる行動も「自己刺激行動」の一つだったことに気づきました。
参考:ASDの子どもに見られる「自己刺激行動」とは?その意味と対応法を解説 | 特別支援教育案内所
参考:自閉症児の自己刺激行動とは何か。止めたほうがいいの? | 発達障害専門のABA教室 Haffyブログ
息子と関わってくれている方に相談した結果、学校と家庭と放課後等デイサービスで長期的に見守りながら環境を整えていくことにしました。

つめかみやものなめは「安心したいサイン」と受けとめて
無理にやめさせず、気にしすぎないように!
支援級・小学1年生|息子の気になった学習面の課題
生活面だけでなく、勉強の場面でも息子のつまずきはありました。
特に「交流級(通常級)での授業」「苦手な体育」「手先を使う活動」は、サポートの必要性を実感しました。
交流級での心配なこと
担任の一斉指示が聞けていない
先生にお願いして、何度か普段の授業の様子を見させてもらいました。

息子の小学校は「いつでも見に来てください!」と言ってくれるのでありがたいです。
すると、交流級の授業で担任の先生がクラス全員に向けて出す一斉指示を息子が聞いていない場面がたくさんありました。

声をかけたくてもガマンして、見守りました。
一部、先生の指示を聞いて動いている時もありましたが…。
息子の様子を見て、近くで待機している補助の先生が個別で指示を伝えたり、周りの子の動きを見て判断しているため、指示が通るまでのタイムラグを感じました。

このままでは、通常級のスピードについていくのは難しそう…。
待ち時間の過ごし方
もう一つ、交流級の様子を見て気になったのが、通常級の待ち時間の長さです。
通常級では、クラスみんなが同じスピードで授業を進めていきます。
そのため、先生が他の子を見ている間や、課題を終えて次を待つ時間が多いです。
待つのが苦手な息子のこんな行動が気になりました。

終始ハラハラしながら見守りましたが、
最後まで自分の席に座って参加できたところは、ほめたいと思います!
体育でつまずく(ドッジボール・運動会・なわとび)
発達性協調運動障害(DCD)の疑いのある息子にとって、体育は特に苦手な分野です。
発達性協調運動障害(DCD)とは大きな病気やケガがないのにもかかわらず、運動の不器用さが極めて大きい障害のことです。
ドッジボールはボールに当たってしまうことへの恐怖心が強く、「ドッジボールはイヤだ!」と珍しく息子が言ってきました。
また、なわとびは1回も跳ぶことができませんでした。
さらに、運動会の練習の時期は特に、疲れや緊張からか…息子の気になる行動が目立ちました。

息子の負担を強く感じて、どう支えたらよいのか悩みました。
手先の不器用さで困ること
字が上手くかけない
息子が文字を書く時に、マスからはみ出してしまう、文字の大きさがバラバラ、字がうすい…など、気になることがたくさんあります。
でも、始めのうちは、文字を書くことが嫌いにならないように「書く楽しさ」を優先して、細かい部分はあまり言わないようにしていました。

今は、「字の形」「トメ・ハネ」などの細かい指導も学校でやっています。
定規で直線がかけない
算数が得意な息子ですが、直線を引く問題では全く点数が取れずに悔しい思いをしました。
息子は定規を押さえて直線を引くのが難しく、どうしてもズレてしまいます。
今後も、図形を描く問題や、分度器やコンパスなど他の道具を使う場面も出てくるので心配なポイントです。

サポートの必要性を強く感じます。
絵の具のふたがあけられない
図工では絵の具のチューブのふたをあけられず、いつも補助の先生にあけてもらっていたようです。
あけやすいキャップの絵の具を探すなどの工夫をしながら、自分であけられる経験を積むようにしています。
給食では牛乳瓶やゼリーのふたがあけられない
給食の時間でも「あけられない」場面がたくさんあります。
特に牛乳瓶は毎日給食に出てくるので、息子にとっては毎日大きな試練です。
ですが、支援級の先生達がさりげなくフォローしてくれてとても助かりました。
支援級での親のサポートで大変だったこと
1年生の間は「学校で頑張る息子」を支えるために、家庭でもいろいろなフォローが必要でした。
特に、登下校や宿題は毎日のことで、親のサポートなしでは難しい場面も多く、工夫を重ねながら過ごした1年でした。
登下校の付き添い
入学当初はひとりでの登下校が難しく、毎日学校まで付き添っていました。

いつまで、付き添っていけばいいのか…?
ゆくゆくは息子に一人で学校に行ってほしい気持ちがあったので、どうやって一人で行けるようにサポートをしていこうか悩みました。
集団登校の大変さ
毎日、上級生のスピードに置いていかれないように、列に合わせて前の子についていくのが大変でした。
また、周りは友だち同士で楽しく会話しながら歩く中、親子共に周りになじめず疎外感を感じることもあり、始めのうちは負担が大きかったです。
雨の日は感覚過敏でさらに大変
息子には「感覚過敏」があり、服がぬれる感触が嫌いです。
感覚過敏は、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)や、体の内部感覚(固有受容覚、前庭覚など)から入ってくる情報に対する脳での処理の仕方に偏りがあることで生じる特性です。
刺激に対して脳が過剰に反応し、不快感や苦痛を感じやすくなります。

雨の日は不機嫌で、登下校がいつも以上に大変でした。
転ぶことが多く、歩道橋の上り下りがぎこちない
体幹が弱く、よくつまずいて転んでしまうことも多かったです。
転んでしまうと、泣き叫んで立ち直るのに時間がかかるので、なだめながら学校に行くこともありました。
また、通学路の途中に歩道橋があり、上り下りが不安定で、大きなケガにつながらないか怖かったです。
階段を左右の足で交互に下りられずに1段ずつ両足で下りるので、列の流れを止めてしまったり…
下りた直後は前の子との間が空いてしまっていることが多く、駆け足で移動したり…
このように、登下校に関しては不安なポイントがたくさんありました。
宿題の取り組みと習慣づけ
また、息子の宿題の取り組みについても習慣になるまでは苦労しました。
就学前は息子がやりたい時や息子の気分がのっている時に家庭学習でドリルやワークに取り組んでいました。
しかし、小学校では毎日決まった量の宿題が出るため、息子の気分に合わせるのではなく、毎日取り組めるように考えないといけません。
そこで、私は息子の「こだわり」を上手く利用できないか考えました。
わが家のASDの息子はこだわりが強めです。
自分ルールやルーティンを好み、それをやらないと落ち着かない部分では、日常生活で周囲を困らせる場面が多々あります。
ですが、「宿題」を息子のルーティンにできれば、息子の「こだわり」が良い方向に活かせると思いました。

「宿題」を息子のルーティンにするには…?
宿題の取り組みルールを決める
家庭内のルールを明確にして、毎日ルールを淡々と伝えることを繰り返しました。

決めたことは変えずに、一貫した姿勢で対応しましょう!
これまでに、息子が疲れている時や気分が乗らない時もありました。
親子でケンカになったこともあります。
それでも、宿題が終わるまでは、私もテレビやスマホを見ないようにして、一緒に毎日取り組みました。
そのおかげで、「学校から帰ったら宿題をする」ことが習慣化され、私が言わなくても自分で取り組めるようになりました。
スケジュールに予定を書いておく
また、ホワイトボードに宿題や予定を書き出して見通しが持てる工夫をすることも効果的でした。
事前に分かることで、息子の気持ちの整理がつきやすく、切り替えもスムーズにできるようになりました。
宿題の取り組みで気をつけているポイント
ただし、わが家では宿題の完成度は甘めにしています。
宿題に取り組めたことをほめて、「まずは、提出できること!」を優先しています。
その理由は、指摘や注意をしすぎると、息子がやる気や自信を失ってやらなくなってしまうからです。
間違いをどこまで指摘するか、常に加減を意識して、本人が嫌にならない程度にとどめるように気をつけています。
支援級・小学1年生でASD息子ができるようになったこと
入学当初は「小学校生活が送れるのかな?」と不安でいっぱいでした。
でも、支援級で過ごした1年間を振り返ると、息子の成長がたくさん見えてきました。
自分でできることが増えた
日常生活の中で、親のサポートがないとできなかったことが、少しずつ息子自身の力でできるようになりました。
朝の準備を自分でできるようになった
毎日、朝の準備や家を出る時間が決まっているので、何時までに食べ終わって何時までに準備をしたらよいのか、自分で次の行動を見通せるようになりました。
おかげで、朝の支度をスムーズにできる日が増えました。
時間割を見て、次の授業の準備と移動が一人できる
支援級では、一人ひとり時間割が違うので、毎日先生がそれぞれの時間割を掲示してくれます。
その時間割を見ながら、自分で教科書やノートを用意して次の授業に移動できるようになりました。
先生や友だちとの関わりが増えた
最初は一人でいることが多かった息子も、少しずつクラスの友だちや先生に心を開いていきました。
まずは、担任や補助の先生との関りが増えました。
息子から先生たちに話しかけることが増えて、「よく話すようになった」「明るくなった」と、先生から聞くようになりました。
それから、「同じ情緒クラスの上級生の子が本を読んでいるのを遠目から見ていた」「クラスの子たちが遊んでいる近くにいてほほ笑んでいた」など、クラスの子たちを気にする様子が見られるようになりました。
さらに、「となりの知的クラスに遊びに行っていた」「自分からはいかないが相手から声をかけてくれると一緒に遊ぶ」と、先生が教えてくれ、少しずつ関わりが広がっていく成長を感じられて嬉しかったです。
支援級で、友だちとの関わりや遊び方のルールを息子のペースで学べたことは、とてもよかったと感じます。

他にもこんなにできることが増えました!
まとめ|支援級の1年間をふりかえって
入学前は「支援級でよかったかな?」と不安でいっぱいでした。
実際に支援級に通って、困ることや戸惑うこともたくさんありました。
けれど、1年を振り返ると、息子のペースで確実に成長できたと感じます。
支援級での丁寧なサポートのおかげで、息子は安心してチャレンジでき、力をつけることができました。
「支援級を選んでよかった!」と心から思っています。
また、支援級での1年目は、親にとっても試行錯誤の連続で、学ぶことがたくさんありました。
困ったことがあれば先生と一緒に考えたり、工夫しながら家庭でサポートしたり。
子どもと一緒に、親も成長できたと感じています。

「一歩ずつ、息子のペースで前に進めばいい」と自信が持てるようになりました!