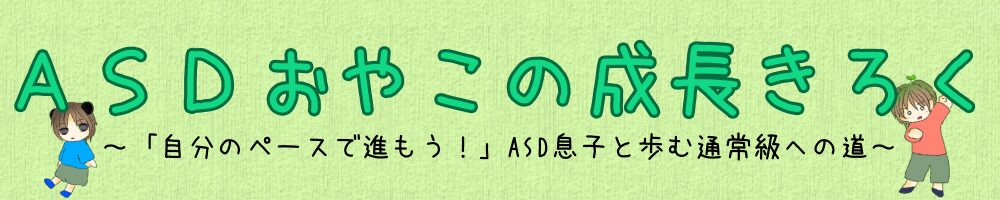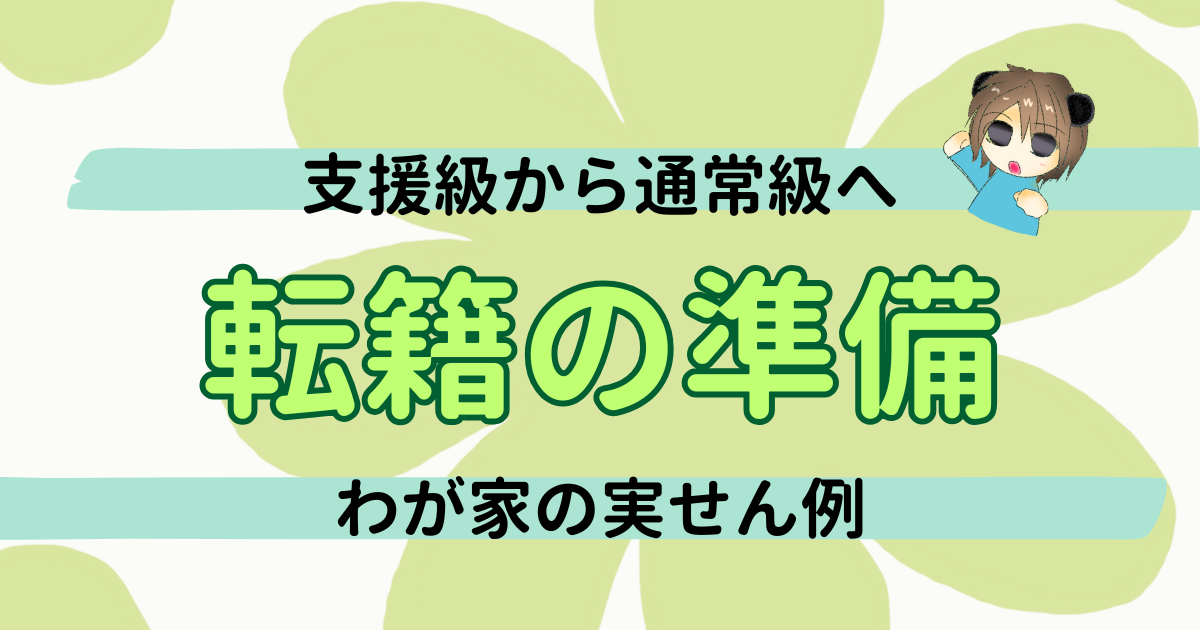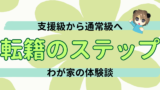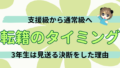我が家のASDの息子は、現在小学2年生で支援級に在籍しています。
小学校に入学した時から通常級への転籍を考えており、そのためには少しずつ準備を重ねていくことが大切だと感じています。
この記事では、我が家で実際に取り組んでいる通常級への転籍に向けた準備についてまとめました。
自立の習慣づけや学習面での工夫、そして子どもが安心して過ごせる環境づくりなど…。
同じように通常級への転籍を考えているママやパパにとって、少しでもヒントが見つかるように具体的な実践例を紹介していきます。
「支援級から通常級への転籍」全体の流れを紹介//
通常級への転籍に向けて家庭で取り組んだ準備リスト
通常級への転籍は、子どもにとっても親にとっても大きな変化です。
そのため、家庭で少しずつ準備を重ねることが大切だと感じています。
まず、通常級への転籍に向けて実際に我が家で取り組んでいることを紹介します。

少しずつ「自信」を育てていこう!
①自立力を育てる習慣づくり
通常級で過ごすためには、学習面の力だけでなく「自分で行動できる力」が必要です。
そこで、我が家では、日常生活の中で自分でできる経験を少しずつ積めるように工夫しています。
例えば、登下校は標識やお店を目印にして、「今日はどこまでにする?」「標識か信号のどっちまでがいい?」と、息子に目標を決めさせて、1人で行ける距離を少しずつのばしています。
身支度や持ち物は、最初は一緒に手助けをしながら、次第にできる部分は息子に任せ、自分でできることを少しずつ増やしています。
また、予定をホワイトボードやカレンダーに書き出し、常に自分で確認できるようしておくこともおすすめです。

最近では、分からない予定があると息子から聞いてくるようになりました!
②学習面のフォローと配慮
学習面では息子のペースを大切にしながら、自主的に取り組めるようにフォローしています。
まず、作業療法で正しい鉛筆の持ち方を教わり、家でも繰り返し練習しました。

鉛筆を持つこと自体が嫌にならないように
無理せず少しずつ練習することがポイントです。
1日1回でもチャレンジできたらOKとしていました!
そして、宿題は「学校から帰ってすぐに取り組むこと」「宿題が終わってから遊ぶ」ルールを徹底しました。
疲れている時は宿題の量を調整して、無理なく進められるように工夫しています。
また、息子は手の不器用さがあり、一生懸命書いても字が枠からはみ出したり、字を丁寧に書くことは苦手です。
そのため、指摘しすぎてやる気をなくさないように、宿題が終わったら「今日も書けたね」「最後までできたね」と声をかけるように意識しています。

前向きな言葉で本人のやる気や学習への自信を育てよう!
③落ち着ける環境づくり
学校で頑張っている分、家庭では安心して過ごせるように、息子の過ごしやすい環境を整えています。
まず、生活リズムが崩れると心も不安定になりやすいため、「起床・食事・入浴・就寝」は毎日できるだけ同じ時間に行っています。
また、ホワイトボードに週間・月間のスケジュールを貼り、息子がいつでも確認できるようにしています。
見通しが持てると気持ちの整理ができ、気持ちの切り替えもスムーズにできます。
さらに、「これは絶対にダメ」という線引きを明確にした上で、家ではできる限り、息子の「こだわり」を自由にさせています。

「こだわり」は息子の心の安定のために必要です。
上手く「こだわり」とつき合っていきましょう!
④夫婦で方向性を合わせる
通常級への転籍は、子どもの成長や将来を考える大切な決断です。
そのため、夫婦の意見や方向性を合わせておくことがとても大切になります。
我が家では、夫婦で意見が合わないことが多く、時間をかけて何度も話し合いました。
100%完璧に同じ方向性にすることは難しいですが、お互いの意見を整理しながら歩み寄るようにしています。
また、連絡帳の内容を一緒に確認したり、個人懇談会での話を報告するなど、普段から学校とのやり取りを夫婦で共有しておきましょう。

話し合いがスムーズに進むのでおすすめです!
⑤子どもの力量を把握する
転籍を検討するうえで、子どもの得意・不得意をしっかり把握しておくことは大切です。
発達検査は、学習面・生活面の特徴を客観的に知る大きな手がかりになります。
また、障害者手帳を取得すると、学校との連携がスムーズになったり、必要な支援を受けやすくなる可能性が高くなります。

ただし、発達検査も障害者手帳も任意なので、絶対やらないといけないものではありません。
必要に応じて検討しましょう!
さらに、定期的に授業の様子を見学しておくと、本人が実際にどのように過ごしているか、どんな場面で困っているかを具体的に知ることができます。
通常級への転籍をスムーズに行うために!学校への相談・確認リスト
次に、家庭での準備を進めるのと同じくらい大切なのが、学校との連携です。
通常級で安心して過ごすためには、学校や先生に子どもの特性や家庭での取り組みを理解してもらい、あらかじめ配慮や支援を共有しておく必要があります。
ここからは、実際に我が家が、入学してからこれまでに行った、学校への相談や確認したことをリストにして紹介します。
①本人の困りごとや心配なことを伝える
新しい学年になって先生が変わるタイミングでは、お子さんの特性や心配なことを共有しておくことが大切です。
困りごとだけでなく、どう対応すると落ち着けるのか「サポート方法」を一緒に伝えておくことで、対応してもらいやすくなります。

息子の場合は…
「こだわりの強さ」「言葉の遅れ」「手先の不器用さ」「運動が苦手」「感覚過敏」「かんしゃく」で困っていることや対応方法を先生に伝えました。
②交流級の様子を詳しく聞く
交流級での様子を詳しく把握しておくと、転籍のタイミングを見極める判断材料になります。
お子さんが「どの場面でつまずきやすいのか」「どのような支援が効果的か」を事前に整理しておきましょう。

転籍してから慌てないように、事前に対策を考えます!
③学習面での困りごとを共有する
学習面の心配や配慮してほしいことを先生に伝えることで、先生がお子さんに合った指導や補助を計画しやすくなります。
転籍後の学習の不安を軽減するためにも、細かく共有しておくことが大切です。

できるかどうかは先生の判断に任せて、気になったことは伝えるように心がけています。
④家庭での様子や放課後デイサービスでの取り組みを伝える
転籍に向けて、家庭や放課後デイサービスでの様子を学校に共有しておくことも大切なポイントです。
お子さんの状況を包括的に理解してもらえ、学校での支援と連携しやすくなります。

息子の混乱を防ぐために!
情報共有を密にして、支援やサポートの方向性を合わせています。
⑤転籍を希望していることを早めに伝える
通常級への転籍を考えている場合、早めに希望を学校に伝えておくことが大切です。
事前に伝えることで、学校や先生が授業や支援体制を調整しやすくなります。

息子にとっても無理のない準備ができます!
通常級への転籍に備えるために!放課後デイサービスへの依頼リスト
また、通常級への転籍を目指す際は、家庭や学校と合わせて放課後デイサービスの支援を活用しましょう。
放課後デイサービスでは「集団の中での学び」や「社会性を育てる練習」として、家庭や学校だけでは得られないさまざまな経験ができます。
ここからは、我が家が放課後デイサービスに依頼している内容を整理してお伝えします。

通常級転籍に向けて、息子の自信を強化しよう!
①他者との関わりや新しいことへの興味を広げる

通常級に移ると、活動や人との関わりが増えるけど…大丈夫かな?
放課後デイサービスで新しい体験や楽しい経験を少しずつ重ねていくことで、「やってみたい」気持ちや「やればできる」自信を積み上げることができます。
こうした放課後デイサービスでの経験が、息子の興味や視野を広げてくれ、転籍後の適応につなががっていきます。
②自分の気持ちの伝え方を学ぶ

通常級では、先生や友だちに自分の気持ちを伝える場面が増えるけど…できるかな?
集団の中で過ごすためには、自分の気持ちを相手に伝えることはとても大切な力です。
特に、困ったときに「助けて」と言えるように、放課後デイサービスで困った場面があった都度、職員と一緒に伝え方を練習しながら経験を積んでいます。
また、息子自身で考えて動けるように、すぐに手を差し伸べるのではなく、時には見守ることも大切にしながら対応してもらっています。
③友だちとの関わり方の経験を積む

通常級で友だちと上手に関わっていけるか心配…。
放課後デイサービスでは、家庭や学校では経験しにくい「友だちとの関わり方」を実際の遊びや活動を通して練習できます。
友だちと一緒に過ごす時の順番やルール、友だちと一緒に遊びたい時のアプローチの方法を教えてもらうことで、関わりの幅を広げています。
また、一方的に話してしまう癖が出たときには「相手は今どんなことをしているかな?」と声をかけてもらい、相手の行動や気持ちに目を向けられるような練習を繰り返しています。
④聞く力をきたえる・言葉を増やす

通常級の授業では先生の一斉指示を聞いて動ける力は必須!
放課後デイサービスでは、職員とマンツーマンでの学習や遊びの中で楽しみながら言葉を身につけられるように取り組んでいます。
また、職員との信頼関係や慣れた友だちとの関わりを通して、息子からたくさん話をするようになりました。
少しずつ「聞く力」と「話す力」を積み重ねることで、息子が自信をもって授業に参加できるようにサポートしてもらっています。
⑤粗大・微細運動を取り入れる

運動が苦手で、手先も不器用で、通常級のペースについていけるかな…?
放課後デイサービスでは、体幹を鍛える活動を取り入れ、学校生活での集中力や安全面に役立てています。
また、楽しみながら身体を動かすことで、運動に対するポジティブな感覚を持てるようにフォローしています。
さらに、手先を使う訓練を取り入れてもらい、鉛筆の操作や道具の扱いなど、学校生活をよりスムーズに送れるようにサポートしてもらっています。
まとめ
我が家の準備はまだ試行錯誤の最中ですが、小さな積み重ねが息子の自信につながっていると感じています。
「自分でできた!」経験を少しずつ増やし、学習への不安を和らげ、安心できる環境を整える…
そんな日々の取り組みが、転籍に向けた土台になります。
また、家庭だけでなく、学校や放課後デイサービスと力を合わせることにより、息子に合ったペースで前に進めてとても心強いです。
同じように転籍を考えているママやパパにとって、「小さな一歩を踏み出すヒント」になれば嬉しく思います。

紹介したのは息子仕様の準備リストになっているので
お子さんの特性や困りごとに合わせてくださいね!