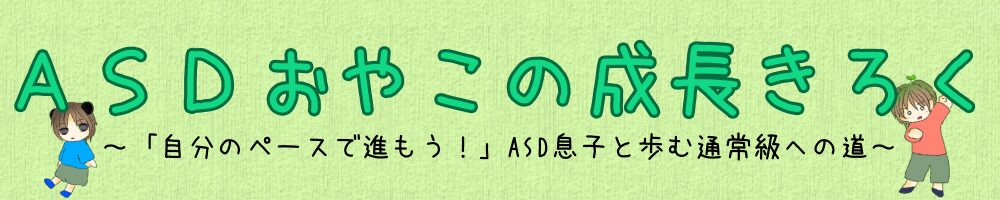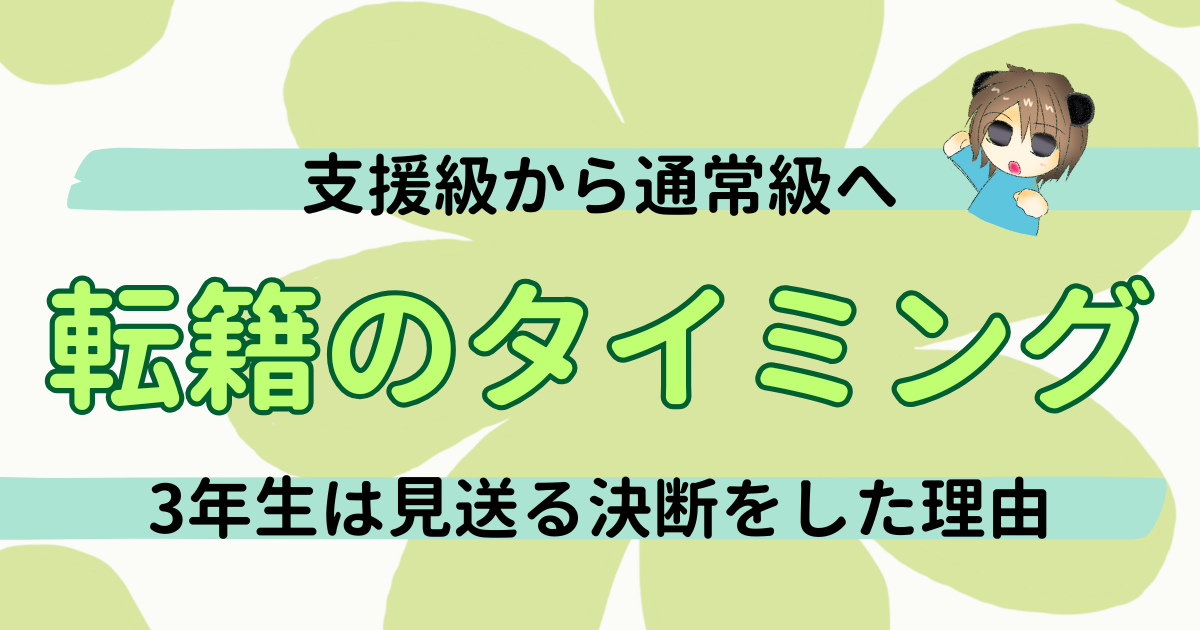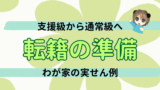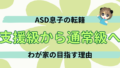「いつ通常級へ転籍をするのがいいのか?」
「どの学年で通常級転籍にチャレンジするのがベストなのか?」

支援級から通常級への転籍のタイミングに悩んでいませんか?
私自身も子どもの通常級への転籍に悩んでいる親の一人です。
我が家のASDの息子は現在小学2年生で入学時から支援級に在籍しています。
我が家では、3年生で通常級へ転籍させたいと考えていましたが、さまざまな理由によって見送ることにしました。
現在は、4年生からの転籍を目指して準備を進めています。
この記事では、転籍を見送った我が家の体験を交えながら、「通常級への転籍のタイミング」のポイントをお伝えします。
3年生からの通常級への転籍を見送った理由
息子が小学校に入学したときから「いつかは通常級へ」という思いがありました。
とはいえ、具体的な転籍のタイミングは私の中で定まっていませんでした。

高学年くらいで通常級へ行けたらいいな…
その一方で、夫は少しでも早いタイミングで通常級へ転籍させたい気持ちが強くありました。
そのため、夫婦で意見が合わず大変でしたが、夫婦で話し合いを重ね、息子が3年生のタイミングで通常級への転籍を目指すことを決めました。
しかし、実際に転籍を進めていくうちに、3年生での転籍は見送る決断をすることに…
その理由を4つにまとめました。
①支援が少ない通常級への不安
通常級に転籍すると「通常級で適応できなかった場合に、支援級にすぐ戻れない」と先生から説明を受けました。

息子の学校では、支援級から通常級に転籍した生徒で支援級に戻ってきた前例がなく、そのため転籍は慎重に進めているようです。
また、通常級に移ると、支援級のような手厚いサポートは期待できません。
息子が安心して学べる環境を失ってしまうかもしれない…。
支援級のサポートのおかげで、できていることが、通常級ではできなくなってしまうかも…。
そんな心配が頭をよぎりました。

学校によって対応は異なるので、転籍を検討している方は学校や担任の先生に直接確認してみてくださいね!
②国語(特に読解や作文)の学習の難しさ
息子は国語の授業が苦手です。
特に、文章を読んで内容を理解したり、自分の考えを書くことが大きな壁となっています。
感想文は白紙のまま提出してしまうことがあり、国語のテストが20点ほどしか取れないこともありました。
また、最近の国語の授業では、グループで意見や感想を言い合う時間が増えており、息子にとっての難易度はより上がっています。

学習面でつまずいて、嫌な思いをたくさんさせてしまうかも…
さらに、3年生になると授業内容が一段と難しくなります。
先生のフォローなしで、息子1人で授業についていけるのか…不安でした。
③通常級に仲のいい友だちがいない
もともと友だちへの興味がうすく、1人で遊ぶことが多かった息子。
ですが、最近では支援級で少しずつ友だちと関わることが増えてきました。
その一方で、通常級では、声をかけてくれるクラスの子は何人かいるものの、一緒に遊べる友だちはいません。

友だちがいなくて、さみしい思いをたくさんさせてしまうかも…
気軽に話せる友だちができず、1人で過ごすことが増え、学校が嫌いになってしまわないか…心配でした。
④息子の気持ちと負担の大きさ
これが一番大きなポイントです。
転籍の相談をした時に、担任の先生や発達外来の主治医、放課後等デイサービスの先生は、通常級に移ったときに息子がつらい思いをしないかを心配していました。
それは、母である私も同感です。
また、「支援級と通常級はどっちがいいか?」息子に聞いてみました。
すると、「どっちでもいい」と返ってきました。
しかし、実際の息子の様子を見ると、交流で通常級に多く参加した日は、疲れて帰ってくることが多く、家でこだわりが強くでることもありました。
言葉には出さないけど、本心はまだ支援級の方がいいと思っているのでは…と感じました。
「頑張ってやりたい気持ち」と「安心して過ごしたい気持ち」の両方が息子の中にあるのかもしれません。
そんな息子の姿を見て、親として、とても悩みました。

頑張れば通常級に行けそうだけど…
結果として、3年生での転籍は息子の気持ちと負担を考えて見送り、4年生に向けて少しずつ準備を整えながら通常級への転籍を目指すことにしました。
通常級への転籍を検討する学年ごとのポイント
支援級から通常級への転籍は、お子さんの発達や環境によってベストな時期は異なります。
早ければよいというものでもなく、親として「どのタイミングで転籍にチャレンジさせるか」を考えるのは、とても難しいことです。
ここでは、一般的によく検討される学年ごとのポイントを整理しました。
低学年(1・2年生)での転籍のメリットと注意点
①通常級のリズムが定着しやすい
低学年であれば「最初からそういうものだ」と受け入れやすいです。
「通常級で過ごす」ことが日常になりやすく、通常級の学校生活のリズムを自然に身につけることができます。
②子ども同士の関係が柔軟で、友だちをつくりやすい
低学年の時期は、子どもたちの人間関係はまだ流動的です。
そのため、途中から通常級に入っても自然に友だちの輪に入れる可能性が高いです。
③早いうちから自立心を育てるチャンスがある
先生のサポートが少ない環境で自分で考えて行動する経験を、低学年のうちから積むことができます。
集団の中で自分で判断して動く機会が自然と増えるため、少しずつ自立心を育てることができます。
④環境の変化が苦手なお子さんには大きな負担になる
低学年から通常級への転籍を検討するメリットはたくさんあります。
しかし、学校生活に慣れるのに時間がかかるタイプのお子さんにとっては、無理に転籍をすすめてしまうと、ストレスや負担になってしまうことがあります。
お子さんの性格や様子をよく見ながら、焦らず慎重に判断することが大切です。
中学年(3・4年生)での転籍のメリットと注意点
①学習スピードや難易度が上がる時期に合わせられる
3・4年生から学習内容が難しくなり、授業速度も上がります。
みんなと同じタイミングでスタートをきることができるので、授業についていきやすいです。
また、低学年の時期に支援級で積み上げてきた基礎があるので、少しずつ理解力や学習習慣を伸ばすチャンスです。
②友だちとの交流の幅を広げやすい
この時期はまだ友だち関係が完全に固定されていません。
そのため、新しい環境でも比較的入りやすく、友だちとの交流の幅を広げやすいです。
低学年で支援級を通じて得た友だちとの関わりの経験をステップアップできるチャンスです。
③落ち着いた雰囲気の中で学べる
3・4年生になると多くのお子さんが小学校の生活に慣れ、クラス全体の雰囲気が落ち着いてきます。
よって、低学年のころよりも、安定した生活リズムで過ごせ、授業も参加しやすくなるでしょう。
④子どもの様子や性格、学習状況を見極める必要がある
支援級でしっかり基礎を固め、自分でできることも増えてきて、中学年で転籍を検討し始めるご家庭も多いのではないでしょうか。
ただし、3・4年生では、低学年よりも授業スピードが速く、学習内容も高度になるので、学習でつまずくことが増えるかもしれません。
さらに、低学年に比べると、友だち関係が固定されつつあります。
すでにできているグループに入りずらく、孤立感や不安が生まれやすい点にも注意が必要です。
お子さんの性格や学習状況、学校でのサポート体制をよく確認し、無理のないタイミングで進めることが大切です。
高学年(5・6年生)での転籍のメリットと注意点
①安定したクラス環境の中でチャレンジできる
クラス全体の生活リズムや学習進度が安定しているため、安心して過ごせる可能性が高いです。
また、本人もこれまでの学校生活に慣れてきているため、新しい環境にも落ち着いて取り組みやすいです。
②支援級で培った力を学習に活かせる
低学年・中学年の時期に支援級で基礎的な学習や生活習慣を身につけているので、高学年で通常級に移っても学習の流れに乗りやすいです。
また、本人の理解力や自立心が育ってきており、自分で課題に取り組む力が発揮できます。
③中学校に向けた環境適応のステップをふめる
高学年で通常級に転籍することは、中学校生活を見据えた大切なステップになります。
支援級で身につけた基礎を活かしながら、少しずつ新しい環境に慣れる経験ができます。
④心理的な負担や自己肯定感低下の可能性
高学年になり、お子さんのできることが増えている一方で、学習内容の難易度はぐっと上がり、中学校への準備も始まるため、負担が大きいです。
また、クラスの人間関係がある程度できあがっており、孤立感や不安を感じてしまうかもしれません。
さらに、新しい環境に慣れるまでに時間がかかってしまうと、「自分はできない」と感じる場面も出てくるので注意が必要です。
お子さんの様子をよく観察し、環境の変化に伴う負担やストレスへの配慮が必要です。
転籍のベストなタイミングは、「子どもの力が伸びてきたとき」だけではなく、「お子さんが安心してチャレンジできる環境が整っているか」にも大きく左右されます。
学校と相談しながら、お子さんに合った時期を見極めていくことが大切です。
4年生の転籍を目指して準備し始めたこと
3年生での転籍を見送った今、4年生からの転籍に向けて少しずつ準備を始めています。
「あせらず!でも、確実に自信をつけていく!」ことが、通常級への転籍をスムーズ進るためには必要です。
我が家の準備のポイントは、「自立」「友達関係」「学習」の3つです。
①支援を少しずつ減らして、できることを増やす
自信をもって通常級にのぞめるように、息子が1人でできることを増やすことが大切です。
そのために、支援級で受けていたサポートを少しずつ減らしてほしいと支援級の担任の先生に伝えました。

「困った時に自分で言えるように、本人が言ってくるまで見守ってほしい!」と先生にお願いしました。
家庭でも、宿題の取り組みや明日の持ち物の準備など、親が手伝っていたことを少しずつ本人に任せていこうと思っています。
②友だちの関わり方の経験を積む
通常級にいくと、友だちとの関わりや集団行動が増えます。
そのため、自分から困った時に友だちに声をかけられるように、友だちとの関わり方をたくさん経験する必要があります。
支援級や放課後等デイサービスでの少人数で慣れた友だちとの関わりを大切にしながら、やりとりの経験を積んでいます。

まずは、支援級や放課後等デイサービスでたくさん練習しよう!
③国語力を伸ばす
国語は息子が特に苦手とする教科です。
そこで、少しずつ力をつけられるように、家庭・学校・放課後等デイサービスで支援しています。
家庭では、毎日の学校の宿題を一緒に確認し、分からない部分は丁寧に説明しています。

なかなか理解してくれず、イライラしてしまうこともありますが…
息子のペースで少しずつ理解が広がっているのを日々感じます!
学校では、国語の中でも特に苦手な読解や作文など、つまずきやすい部分を個別にサポートしてくれます。
放課後等デイサービスでは、語彙力の強化やビジョントレーニングに取り組んでいます。
④家庭・学校・放課後等デイサービスで連携して支えていく
4年生での通常級転籍に向けた準備は、家庭だけで完結するものではありません。

1人で悩まずに、お子さんの困っていることを整理して伝えよう!
家庭では宿題や生活習慣のサポートを調整しながら自立力を育て、学校では授業や休み時間の中で友だちとの関わり方や学習の基礎を伸ばしてもらっています。
さらに、放課後等デイサービスなどの支援機関と連携することで、集団生活や学習面での実践的な経験を積むことができます。
それぞれの役割を持つ家庭・学校・放課後等デイサービスが力を合わせることで、息子の自信を少しずつ積み重ねることができます。
まとめ
通常級への転籍のタイミングは、学年や環境だけでなく、子どもの発達や性格、家庭の状況によって異なります。
「早ければいい」というわけではなく、お子さんが無理なくチャレンジできる時期を見極めることが大切です。
我が家は、3年生での通常級への転籍を見送りました。
その理由は、学校のサポート体制の不安や学習面での課題、友達関係、本人の負担など、さまざまな現実があったからです。
しかし、転籍を諦めたわけではありません。
4年生での通常級転籍を実現させるために、我が家では以下の取り組みを始めています。
- 家庭や学校での支援を少しずつ減らし、自分でできることを増やす
- 学校や放課後等デイサービスで友だちとの関わり方の経験を積む
- 国語を中心とした学習面の基礎力を伸ばす
家庭や学校・放課後等デイサービスで情報共有をしながら、息子の「自信」を少しずつ育てています。
転籍のタイミングに悩んでいるママやパパにとって、我が家の経験が少しでも参考や安心につながれば嬉しいです。